レコードマネージャの役割
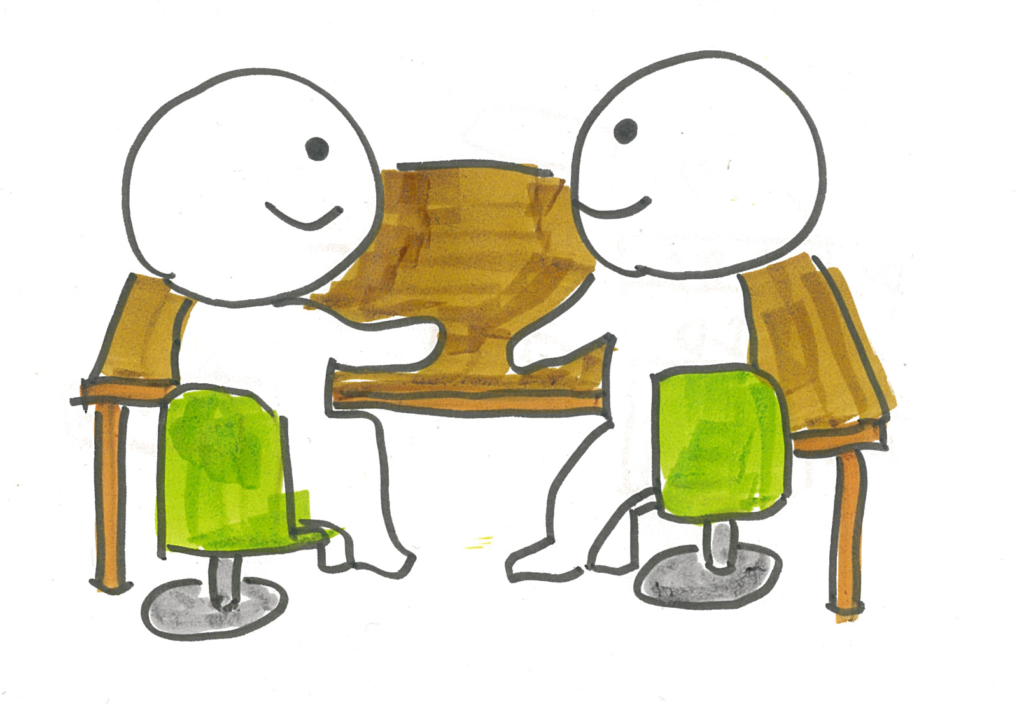
レコードマネージャ
日本ではあまり定着していない職業に「レコードマネージャー(記録管理者)」という職業がある。日本では、文書管理責任者のような名目はあるが、実態は伴っていなことがほとんどである。
欧米では、レコードマネージャーが組織における記録管理体制を仕切っている。アメリカでの大手企業のレコードマネージャーへのインタビューによる調査が行われた。
対象となったレコードマネージャのうち45%はハイレベルの資格認定を取得していた。5%は修士か博士を取得していた。
実質と形式
日本では文書管理と言えば大方は総務部門であるがアメリカの調査では総務部門が33%、法務部門が25%、IT部門が15%であったが、今後はIT部門が増えてくる見込みである。
レコードマネージャーの役割は、
- 記録管理方針
- 分類体系
- 保存期間の基準設定
- 運用手順
- 記録管理教育
- 重要記録の保護(アーカイブ)
- 電子化
などとなっている。
レコードマネージャーは部門の長と連携して記録管理体制を強化している。教育は新人教育だけにとどまらず、管理職教育までカバーしている。
人材の流動と実質的組織運営
日本では規定や規則は作るけれど、そのルールを定着させるための具体的プロセスが用意されていないことが多い。決めたことを推進・順守・実施しなければ、それがどんなに美麗な言葉を尽くしていたとしても実行・定着が伴わない。
このような状況に対して、日本ではなぜ、このような取り組みをしてこなかったのだろうか。それはひとえに、組織にとっての記録管理を重要なこととは認識していないことにある。
なぜなら、終身雇用問い制度において、組織運営のノウハウは「属人管理」で行ってきたからである。
アベノマスクという脱法的無記録管理
悪名高かった「アベノマスク」もメディアが、その悪辣さを意図的に取り上げないため風化しつつある。使った費用は543億円。8000万枚を廃棄。対応管理した官僚のセリフでは、仕様書もなく契約書もなくメールだけで440億円を発注し、製造、品質、納品、発送などを管理し、そのメールはメールボックスがいっぱいになったから消去したとのたまっている。
こんな連中を処罰もできなければ「レコードマネジメント」なんて言葉は、日本においてはお笑い種でしかない。
民間企業においても、組織間競争に打ち勝つために、記録管理の重要性が認識されていない。
情報の管理には「活用」という側面があり、ここに気が付いているか否かで、競争力に差が付く時代になっている。日本の記録管理の背景には、「年功序列・終身雇用」による属人管理と性善説による「組織」形態が作用している。
人材の流動化と組織運営
人材の流動化はGAFAMあたりから盛んにおこなわれだしている。なぜなら、旧態の人材はどんどん不要になり、低評価なマネージャも数の内で雇用していたけれど、新たなスキルを持つ人材入れ替えるために大量にレイオフを断行しだしている。
レイオフの仕方も強烈で「各マネージャが掌握する人材の下から何パーセントをレイオフしろ」のような切り方をすると同時にマネージャ1人当たりが掌握する人員の数を増やして結果を数値管理する。
いまは、「AI人材」に入れ替えていくが、トレンドは変わっていく。
日本企業がこのような採用・解雇をしていくことができるためには法改正が必要だし、公務員などは全くこうしたことから無縁であるが、1700も自治体があって、そこに首長がいて議会があって居眠り議員が跋扈している。
これを170くらいに集約して、道州制にぶら下げれば各道州に自治体20くらいで済むようになる。
無能な人材がいなくなって「誰もいなくなる」としても、困らないようにするのがレコードマネージャの役割である。

