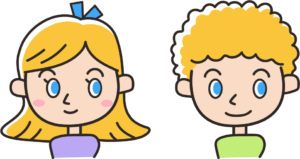天才の2類型
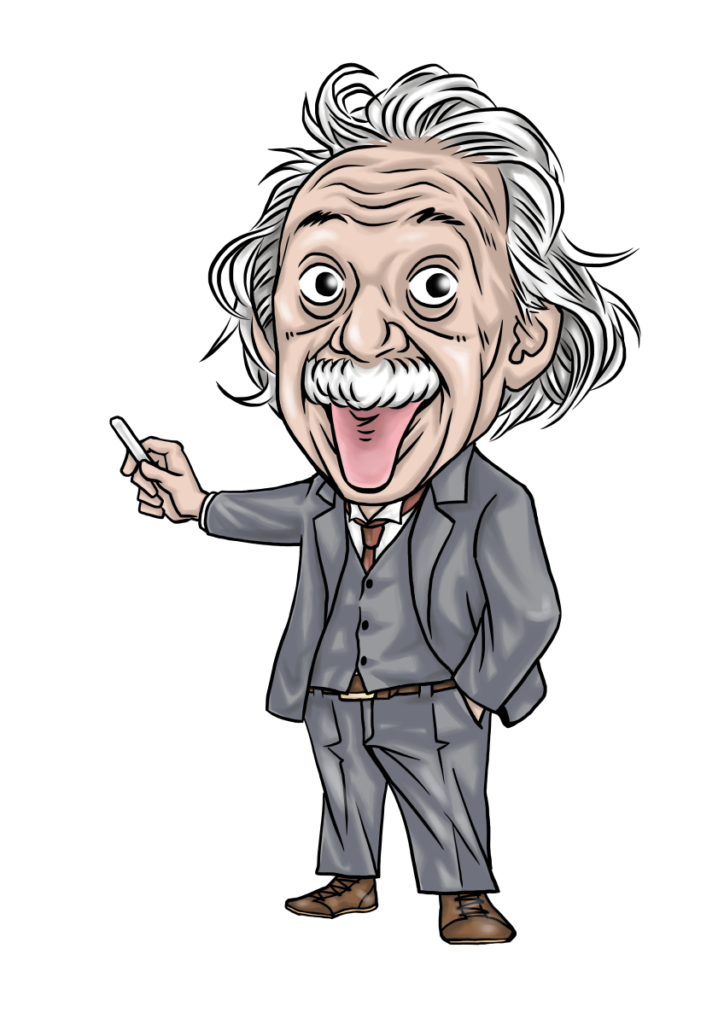
先天的天才と後天的天才のいるそうです。「後天的な天才」といっても、生まれつき平均以上の知能(IQ115~130前後)の持ち主が、適切な早期教育を受けることで、さらにその特性を伸ばし、高い能力を身につける「天才」のこと。
2018年でアメリカで「ギフテッド認定」を受けた子が6.8%あったそうです。
「後天的天才」は、日本人、韓国人、中国人などのアジア人に特に多くいるようです。アメリカでギフテッド判定を受けた子どもの人種構成を見ると、アジア人が他の人種の2倍近い割合だとか。
ポイントは「子どもの特性に合った教育」と「適切な教育の継続」が必要で、特に「後天的天才」には、油断することなく適切な教育を継続していかなければ、いずれは普通の人になってしまう。
磨き続けなければならないなら、その「天才」は「金」ではないようです。
ということから、著者は本の宣伝になります。「強みを生み出す育て方」という本だそうです。手遅れでない人は、買うなり図書館から借りるなりしてみてください。ちなみに、台東区には4冊あって、いま、22人待ちです。
楽器の天才が時々話題になりますが、楽器演奏の天才はいずれは「AI」で十分になると思います。スタインウェイのショールームで、「Steinway & Sons SPIRIO」という商品が見られるそうです。
これは、実際にスタインウェイで演奏家が弾いたのをデータ化して再現していますが、この先に、演奏家の演奏方法をAIで分析すれば、演奏家が弾いていない曲であっても、「この曲をグールド風に弾いて」のようなことができると思います。
データ化していなかった時代の演奏を、克明に再現したデータもあるようです。スタインウェイのショールームで、グレン・グールドの演奏を見せてもらっています。
話し戻して「後天的天才」は磨き続けなければ天才を維持できないとなると、なんだか幸せな感じがしません。かといって「先天的天才」だとしても、それも幸せな感じがしないのは、自分がぼんくらだからなのでしょう。
じゃ、ぼんくらが幸せなのかというと、それも幸せな感じがしません。友達が多いと幸せだという人もいますが、「友達」の定義を明確にしなければならないでしょう。
単に「仲がいい」だけなら大方は「仲がいいフリ」だと思います。人生において、加山雄三ばりに「幸せだな」というシーンがあったかと思うと、おそらく、それに該当しそうな出来事としては「ギザ十」を見つけたときと、道を歩いていて500円玉を拾った時ぐらいだったと思います。
異性であれ、同性であれ、「君といるときが一番幸せなんだ」というような経験もありません。
原題は「Love is a many splendored thing(愛はとてつもなく素晴らしい!)」で、邦題は「慕情」。はたまた「ローマの休日」のようなドラマチックな恋愛がそうそうあるわけでもないし、大方は職場とかサークルのような身近なところで妥協の産物のような「恋」にしているような気がします。
「愛」があれば「たくさん素晴らしいこと」と同等だそうです。やはり、天才よりは異性に持てることのほうが幸せになれそうですが、複数の異性との思い出を役所や会社のパソコンに記録したり、選挙に勝った政党党首が女性とホテルにしけこんだりするのも、永続性の無い「幸せ」のような気がします。
結局は、背伸びをしない、自分の身の丈(器)に合った生き方が、ドラマチックではないけれど、死ぬときにはさほど後悔しないで済みそうです。
ぼんくらの人生として目指すべきは「不幸ではない」ことをもって良しとする生き方なのでしょう。
追記
両親が愛し合っていると感じる子供(大学生)は、恋人がいることが多く、異性との性的関係が少ないそうで、逆に、両親が愛し合っていないと感じる子供はm更衣人が少なく、異性との性的関係が多い傾向にあるようです。
「Love is a many splendored thing」という環境で巣立つことは、「幸福」という観点からすれば非常に重要なポイントのようです。日本の夫婦はえてして「金」で結びついている部分が少なからずあるということもあって、大人も子供も調査によると幸福度が世界中に比べて低い社会になっているとのことです。
こうなると、個々の個人の問題というよりは「社会の仕組み」に問題があるような気がします。それは政治なのか、教育なのか、経済なのか、それ以外の何かなのかはぼんくらにはわかりません。