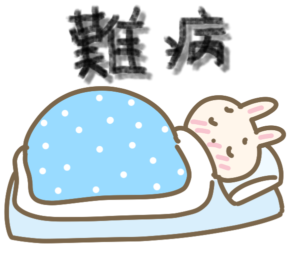「デューデリジェンス」とは?

(Due Diligence)とは、
M&A(企業買収)や投資を行う際に、投資対象企業や物件の価値やリスクを詳細に調査・分析するプロセスを指します。日本語では「適正評価手続き」や「買収監査」とも呼ばれます
とのような説明になっている。
「再生の道」で台東区で名乗りを上げた横山さんと石丸さんとの会話でも、取り上げられていたキーワード。
議会の審議とは「デューデリ」を前提としなければならないはずであるとして、石丸ー横山さんの面接は終わっている。
横山さんは、公的予算の使途は、すべからくがデューデリに合致していなくても公共サービスとしての公共的措置もあることは認めているが、「透明性」と「公益性」が不可欠であることを担保するためには不可欠なパワーワードとして都政に生かさなければならないと指摘している。
今の都政で「透明性」が一番「不透明」な知事と知事与党で運営されているから「再生の道」潰しに躍起になるのだろう。これが国政なら「公安」とか「内閣調査室」などを動員して立候補者の瑕疵探しに夢中になっているはず。東京も警視庁があるからやっているかも。
カイロ大学を卒業したのかなどは、いまだに未解決であるがカイロ大学に問い合わせて卒業証明書を1枚発行すれば済むだけの話である。それをしないということは「やましい」からであって、学歴を詐称した首長を東京に置いたまま、メディアも政権も放置している国は、思想としては「不透明性」と「不公益性」を極めている途上国スタイルそのままであるけれど、有権者はそれを「よし」としているのだからお互い様でもある。
プロジェクションマッピング、お台場噴水、800億円かけた「東京アプリ」、神宮外苑樹木伐採など、着々と知事と知事与党は事を進めているが、そうした首長と都議会忖度議員を選んでいるのは都民だ。
民主主義には「デューデリジェンス」などは、無用の長物なのだろう。
人権デューデリジェンス
企業が自社やサプライチェーンにおける人権リスクを特定・評価し、防止・軽減、改善を図るための継続的な取り組みのことです。具体的には、人権への負の影響を特定し、その防止・軽減策を講じ、取り組みの実効性を評価し、結果を外部に開示するプロセスが含まれます
日本はガイドラインは公表しているものの、いつものごとく企業に対して法的拘束力を持っていない。欧州では2024年に「企業サステナビリティ・デュー・ディリジェンス指令(CSDDD)」が発行され、企業に義務付けられる。
レアアースを買おうとすると、そのレアアースはどのようにして採掘され、精製され手元に届くのかまでの「人権」までに配慮したサプライチェーンを構築しなければ、いつまでたっても途上国の「奴隷」的労働を根絶することはできない。
プロセス
デューデリジェンスのプロセス
一般的なデューデリジェンスのプロセスは以下の通りです。
- 準備段階: 調査チームの組成、調査範囲と方針の決定、秘密保持契約の締結、必要な資料のリストアップなどを行います。
- 資料開示と分析: 対象企業から必要な資料を開示してもらい、財務諸表、契約書、事業計画書などを詳細に分析します。
- 質疑応答とヒアリング: 開示された資料だけでは不明な点や詳細を確認するために、対象企業の経営陣や担当者に対して質疑応答やヒアリングを行います。
- 実地調査: 必要に応じて、対象企業のオフィスや工場などに赴き、現状の確認や関係者へのヒアリングを行います。
- 報告書の作成: これまでの調査結果をまとめ、リスク、評価、提言などを記載した報告書を作成します。
- 最終判断と交渉: デューデリジェンスの結果を踏まえ、買収や投資の最終判断を行い、必要に応じて対象企業と条件交渉を行います。
こんなことを、今の都政でやるはずはない。そのためには首長と議員と官僚幹部を入れ替えなくてはおよそ無理で、そのためには東京都の有権者の入れ替えも不可欠になるから、きっと首都破綻まで無理筋な話で終わるのだろう。
あるいは、都民がある日目覚めて「再生の道」のような考えに基づいて「政治」が変わる日が来れば別の話になる。
とはいえ、政治家が変わっても公務員である官僚が胡坐(あぐら)をかけないような仕組みを作らなければ、いつまでたっても本質は変わらない。