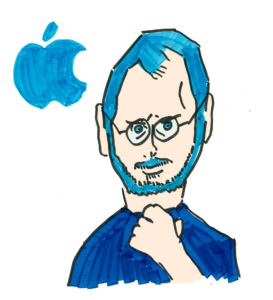「哲学」という学
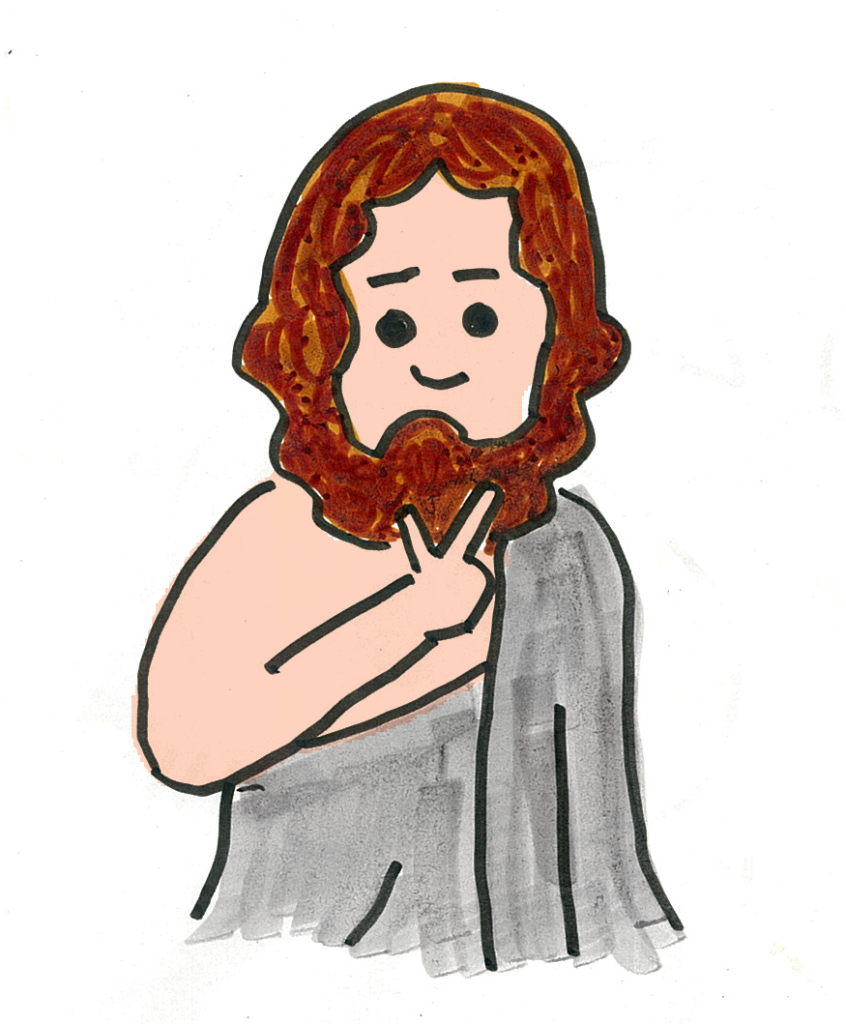
「哲学」は、明治になってから日本に入って来た。とはいえ、日本には「哲学」に相当する、ものの考え方や見方が無かったわけではなかった。
西洋の哲学はギリシアあたりを起源として、各国にそれぞれ、哲学を発展させてきた人々がいて、体系も整っていたものを欧米から学問として教鞭をとっている人材を招いたことに端を発している。
明治11年にフェノロサが25歳で東京大学において教鞭をとった。ハーヴァードで学んでおり、ドイツ哲学を教えた。フェノロサは後に東京美術学校に転じ、そのあとにブッセが東京大学で教鞭をとった。
西田幾多郎によれば、「ドイツ人でも英語で講義した。中々元気のよい講義をする人で、調子附いて来ると、いつの間にか、英語の発音がドイツ語的となった」と評している。ドイツ人が英語で授業をしたということは、学生も英語で授業を受けていたということ。
ブッセがドイツへ帰国するときに夏目漱石がクラスを代表してブッセ宛に「別離の挨拶」を英文で書いている。ブッセと入れ替わりに来日したのが、ケーベルである。ケーベルは21年間在日し、大正3年まで東京大学に在職した。
夏目漱石は「ケーベル先生」というエッセーを書いている。
というのが、明治に新たに入って来た「哲学」の沿革である。この「哲学」という熟語は西周が作語している。
西周は、文政12年(1829)に津和野で生まれ、漢学を身に着け藩校で蘭学を学んだ。安政4年には蕃書調所の教授になり、ここで哲学や西欧の学問を研究した。文久2年(1862)に榎本武揚らとオランダに留学し、法学や哲学を学んで慶応元年(1865)に帰国した。
西は、西洋のフィロソフィという言葉を日本に導入する際に、最初は「希哲学」という訳語を用いたが、「哲学」と言う言葉を使い始めることで定着して現在に至っている。
「フィロソフィ」は、「知を愛する」というギリシャ語が語源。
「哲」は「中国語の『折(くじく)』と『口(言葉)』で、『言葉で説いて、くじく』『知恵が優れる』という意味」だそうだ。「知を愛する」というよりは「知をもって相手をくじく」というニュアンスに近い。
この「哲学」となると、明治になってから確立している関係もあって、最澄や空海、本居宣長なども哲学者とは呼ぶことはない。老荘孔孟なども思想家とするが哲学者とは呼ばない。
どうも、哲学というと、日本的にはいまだに違和感が漂っている学問でもある。
おまけ
西周が作った語彙。「哲学」のほか、「芸術」「理性」「科学」「技術」「心理学」「意識」「知識」「概念」「帰納」「演繹」「定義」「命題」「分解」など多くの哲学・科学関係の言葉がある。
西周が特異な才能を持っていただけではなく、努力の人でもあったが、漢学を身に着けていたことも大きい。もし、現代においてはじめて「哲学」が西欧から日本に導入されたなら、現代の学者は「フィロソフィ」とカタカナにするだけなのだろう。受験の点数を上げるために漢学など身に着けている暇はない。
ちなみに、中国では西周が作った「哲学」を老荘孔孟にも充てて使っている。