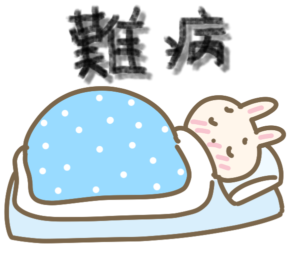「思考の整理学」という「学」

外山滋比古さんの「思考の整理学」
新版の帯を見ると、

とあります。自分には東大も京大も、縁もゆかりもないので残念ながら「バイブル」にはなりえませんでした。「学」と書かれているので、何らかの「知」の体系を解説しながら思考をまとめていくようなメソッドを期待していましたが、単なるエッセー集でしかなかったように受け取りました。
「なになに学」のような「学」が意図するもの
「なになに学」のような「学」が意図するものについて見解を示してください
geminiに上記のように問い合わせてみました。
「〇〇学」という言葉に含まれる「学」という接尾辞は、体系化された知識、研究分野、学問領域といった意味合いを持ちます。しかし、その使われ方は多岐にわたり、意図するものは文脈によって異なります。
「学」が意図するものの主なパターン:
- 伝統的な学問分野:
- 最も一般的な用法で、特定の対象や現象を体系的に研究する分野を指します。例: 経済学、心理学、社会学など。
- これらの「学」は、専門的な研究者によって厳密な方法論に基づいて探求される知識体系を意味します。
- 学際的な研究分野:
- 複数の学問分野を組み合わせ、新たな視点から対象を研究する分野を指します。例: 認知科学、情報科学、環境学など。
- これらの「学」は、既存の学問分野の境界を超えて、複合的な問題に取り組むことを意味します。
- 比較的新しい研究分野や関心領域:
- 近年では、特定の文化現象や社会現象を研究対象とする比較的新しい分野にも「学」が用いられます。例: アニメ学、マンガ学、観光学など。
- これらの「学」は、従来の学問分野では十分に扱われてこなかった対象に、学問的な光を当てることを意味します。
- 特定の技術や実践に関する知識体系:
- 特定の技術や実践に関する知識体系にも「学」が用いられることがあります。例: 経営学、工学、医学など。
- これらの「学」は、理論的な知識だけでなく、実践的な応用も重視する知識体系を意味します。
- 俗称や比喩的な表現:
- 日常会話やメディアでは、特定の事柄に関する知識やノウハウを指して、比喩的に「〇〇学」と表現することがあります。例: 恋愛学、睡眠学、料理学など。
- これらの「学」は、必ずしも厳密な学問体系を意味するわけではなく、関心や興味の対象をユーモラスに表現する効果があります。
「〇〇学」という言葉は、多様な意味合いを持ちますが、共通して言えるのは、何らかの対象に対する体系的な知識や探求を意味するということです。
「思考実験」で「学」を期待してみる
ということで、何らかの体系を持った「学」を期待するならほかの本を当たるほうがいい。ちなみに「思考実験」という本もある。榛葉豊さんという方が書いている。
科学へのアプローチとして、純粋な思考によるアプローチを難しいテーマを対象に展開していますが、ちょっと扱っている内容が難しいので、自分にとっては「学」になりがたかった。
ただ、「思考実験」の本の但し書きには、いずれも「論理的思考力」が身につくというようなことが書かれている。本を読むだけで論理的思考力が身に付け場、これに越したことはないので、いずれはチャレンジしてみようと思っている。
思考を整理する主たる目的はいくつかあって、「優先順位をつける」「もやもやをすっきりさせる」「解けない問題を解く」「もやもやをすっきりさせる」「考えもしなかった発想を得る」「過去の考えたことを随時取り出せるようにする」など、多岐にわたる。
ポイントは「取り出し可能」な「整理法」であって、力任せの記憶ではない「手法」になっていることが望ましい。
補足:「あとがき」に発見あり!
「あとがき」で「思う」と「考える」について書かれており、「我思う、ゆえに我あり」は「I Think ~」であるが、「久羅下那州 多陀用幣琉之時」の状態は「I seems to me」の状態であるとしている。
「くらげなす、ただよえるのとき」とは、思考が明確にはなっていない状態であり、定かな形をなすことができなければ「拡散崩壊」して消滅してしまうとある。
まさに、この過程こそが「思考」すべき時であり、「思考」する価値の瞬間でもある。
日本書紀とクラゲ
日本書紀では、日本がまだ、クラゲのようにふにゃふにゃしていたときに神様が降臨することになる。
日本の政治は、この数十年「くらげなす」状態であると言える。まともなリーダーの降臨の予感すらない。「小泉純一郎」あたりから今に至るまでずっと「くらげなす」状態だったような気がする。
それ以前は、記憶にもない。どっちみち「くらげなす」だったと思う。だから「小泉純一郎」あたりにやらせてみれば、面白かろうという程度の選択だったのが「郵政改革」で、結果は惨憺たるものになりつつある。
そろそろ、降臨があってもよさそうな時期になってもらわないと、「拡散崩壊」して消滅してしまうだろう。
クラゲなして漂う国民性
所詮、人間の本質は「くらげなす」であり、虚空を「ただよう」のが本質だと思う。
「ただよう」という状態は、「収斂」でもなければ「拡散」でもない。なにかに「収斂」できるわけでもなく、かといって「拡散」し「崩壊」してしまうほどの覚悟があるわけでもない。
企業活動も政治も「収斂」することが「力」になるが、収斂するということは「個」を喪失することでもある。
今の政治と国民の対応は、まさに「クラゲ為して漂っている」ようなものと言えそうだ。次なる「降臨」を待って、再び「落胆」するもよし、「雀躍」するもよし。