「DD論」という本
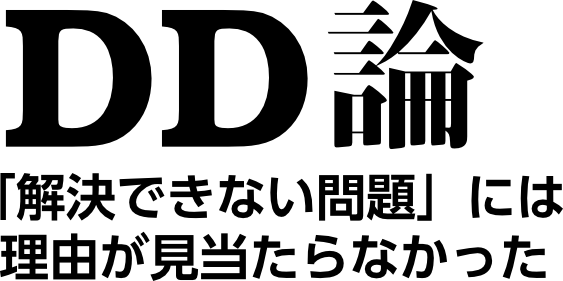
そもそも「DD論」とは何かというと、著者によれば「どっちも、どっち」ということだとしているようだけれど、本の中身は「どっちもどっち」とか「善悪二元論」「リベラルと保守」などの考察になっているような気はしなかった。
全体を支配している文章としては「世相を語るエッセー」という位置づけに近いものであるが、それなりの視点は提供してくれている。
ダーウィンの従兄弟のフランシス・ゴルトンは家畜の品評会において牛の体重あてコンテストの投票用紙を調べたら、参加者全員の平均は、専門家より正確であった。
相互に相談することなく独立した素人判断には間違いも多かったが、専門家の判定より平均が正解に近似していた。
そのことから、ゴルトンは独裁政や貴族政より民主政の方が優れていると結論付けた。
現実には「多様性」とか称して、民族、宗教、政治信条などで徒党を組み、徒党の意向で行動をするようになる。あげくに「派閥」という、さらに利益を追求する小集団で結束するようになり、やくざ組織よろしく「爺」が親分気取りで指令を出すようになる。
そのいい例が日本の政治で、多大なお金を使って「選挙」という愚かな仕組みで選出され、なんの能もなく高禄を食む「議員」の存在は、「政党」という利権団体の中の数字の「1」でしかない。
その数を集めて意思決定をすればゴルトンの「素人」の判断をはるかに下回る。つまり、通常考えられる「民主政」による政治が最良でもなく、最適でもない。
まさに、石丸伸二さんの「再生の道」の手法のほうが、ゴルトンの指摘する「民主政が優れている」とする根拠を示している。逆を言えば、通常の政党政治は、実際には「民意なんて無視」していることは明らかで、単なる「利権」のための団体でしかない。
有権者はというと、ほとんどの人は政治に興味など持っていないし、投票する政党の実態も知らないし、投票しようとしている立候補者の何も知らない。憲法、刑法、民法なんてのもあるのは知っているけれど、内容なんてほとんど知らない。
こんな有権者が投票すること自体に制度の意味があるのか? 有権者が「詳しい」知識を持てば民主政は正常に機能するのか?
そんな意味からして、「再生の道」の今後がどうなるのかには興味が尽きない。
同じ著者から「もっと言ってはいけない」という本も出ていた。図書館から借りてきて目を通してみたものの、内容はかなり低レベル。さしたる科学的根拠もなく「IQ」が格差につながっているような論調。
冒頭で黒人と白人の知能(IQ)差を取り上げて睾丸の重さまでの飛躍的展開に終始している。少し辟易。まともな出版社の所業とは思えない内容で、こうした低レベルな本がチマタを汚染する。

