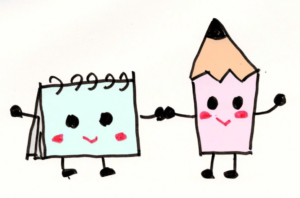オピオイドと自閉スペクトラム症
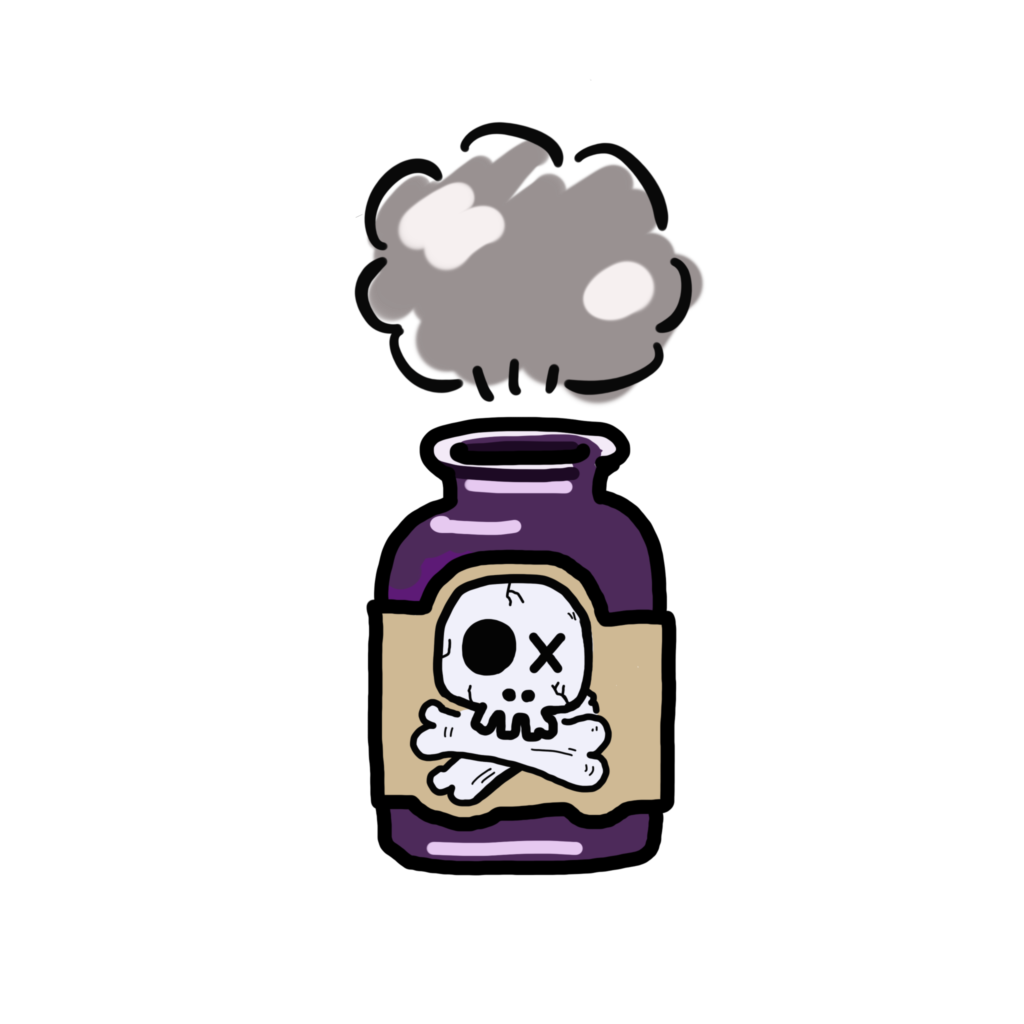
スペクトラム
スペクトラムには「連続」している範囲を意味している。自閉症にも様々な態様あるようで、「1」か「0」の様な分け方ではなく連続体として「スペクトラム」が使われるようになったと、なにかで読んだ。
スペクトラムとすることで、症状ごとへの対応を変えることができる。
議論などをすると「是」か「否」になりがちであるが、意見や信条なども、実施にはスペクトラムになっていることの方が多い。にもかかわらず、テレビなどでは「識者」と称する人たちが「是」か「否」で愚かな論争(口論)を見せモノにしている。
人の思考は「1」か「0」かのデジタルではないが、AIはデジタル処理の結果を「知能」として出力している。
オピオイド
オピオイド(Opioid)は、ケシから採取されるアルカロイドや、そこから合成された化合物、また、体内に存在する内因性の化合物を指す
アルカロイド(オピエート)やその半合成化合物には、モルヒネ、ジアセチルモルヒネ、コデイン、オキシコドンなどが含まれ、合成オピオイドにはフェンタニル、メサドン、ペチジンなどがある
つまりは、天然の「麻薬」。アメリカが問題にしているのが中国製のフェンタニル。
ASDにオピオイド投与
自閉スペクトラム症(ASD)のマウスに低用量のオピオイドを投与したところ、社会性が向上することを広島大学などの研究グループが実証したそうだ。
ASDはモチベーションの維持や社会的コミュニケーションに関する脳領域の機能が何らかの形で阻害されている状態をいう。そこに低用量のオピオイドを投与することで、社会性行動に関わる領域である「内側(ないそく)前頭前皮質」と「側坐核(そくざかく)」という部位が活性化することが分かった。
オピオイドの濃度を上げると、恐怖や不快感を招く働きをもたらすので逆効果になるそうだ。
因果関係
これらの部位の活性化がASDの治療にとってポイントなのか、それとも活性化は薬剤を用いた結果に過ぎず、別の要因があるのかどうかといった細かい因果関係を調べるとのこと。
研究は広島大学、大阪大学、京都大学、塩野義製薬が共同で、日本学術振興会の科学研究費助成事業、中冨健康科学振興財団、アステラス病態代謝研究会、持田記念医学薬学研究財団の助成を受けて実施した。成果は2024年12月6日に米学術誌「JCI インサイト」電子版に掲載され、広島大と阪大が25年2月10日に共同発表した。
相関関係と因果関係
相関関係とは「二つの値の間に関連性がある関係」のこと。一つの値が変化すると、もう一つの値も変化することを指す。
因果関係とは「原因とそれによって生じる結果との関係」のこと。原因の「因」と結果の「果」が組み合わさった言葉。一つの値を原因として、もう一つの値である結果が変化すること。
となると、同じようであるけれど、因果関係には相関関係が内包されているが、相関関係においては必ずしも因果関係が確立しているわけではない。
ここの証明が「科学」には不可欠になる。が、多くの場合、相関が出るとまかり通ってしまうことが多い。とくに、マーケティングなどでは似非科学が横行している。