ゴキブリの謎
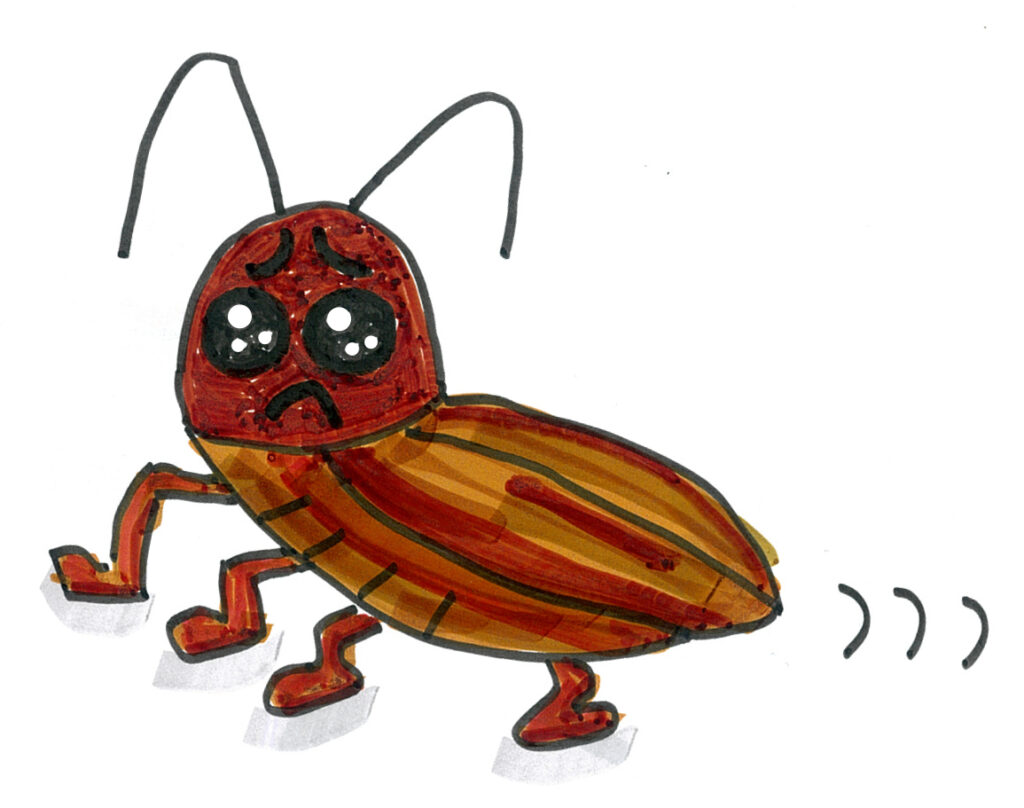
チャバネゴキブリは英語で「German cockroach(ドイツゴキブリ)」と呼ばれるが、今では南極大陸を除くすべての大陸に生息しており、地球上に生息する4600種のゴキブリの中で最も数が多い。
3億8千年前に地球上に出現した古い系統の昆虫で、形態的に大きな変化をしないまま、現在もたくましく繁栄している昆虫。
ゴキブリの語源は「御器囓り」で、蓋付きお椀に齧りつく虫という意味。明治22年に出版された「中等教育・動物学教科書」(飯島魁 著)で、「蜚蠊」という漢字にゴキカジリではなく、ゴキブリとルビを振ってしまったとある。
「蜚(ヒ)」は、漢字単独で「あぶらむし」のことだそうだ。「蠊」は「レン」と読み、「蜚蠊(ヒレン)」でゴキブリを意味する。
科学者は、6大陸17カ国で捕獲したチャバネゴキブリ281匹のDNAを分析し、それらが互いにどの程度の近縁関係にあるかを調べた。
分析の結果は、チャバネゴキブリが約2100年前に現在のインドとミャンマーにあたる地域でオキナワチャバネゴキブリ(Blattella asahinai)から進化したことを示していた。
英語で「German cockroach」のように「German」がついている理由を調べると、「スウェーデン人博物学者のカール・フォン・リンネがドイツからの郵便で本種のサンプルを受け取ったことに由来する」とのことで、特段、「ドイツ」の名称には意味はない。
チャバネゴキブリはやがて野生を捨てて人間のそばに潜んで生きるようになり、約1200年前、中東に進出した。その後、飛躍的に地理的な広がりを示したのは約390年前にヨーロッパ諸国の植民地活動が急速に進んだことによる。
チャバネゴキブリが進出すると、その地域にいた原種のゴキブリはチャバネゴキブリに駆逐されてしまう。
人間が何年にもわたり、ブドウ糖(グルコース)を混ぜた毒でゴキブリをおびき寄せて駆除しようとしてきたが、最近のチャバネゴキブリには、ブドウ糖を避ける新たな系統が生じているとも言われている。

