マグロの刺身の食べごろ
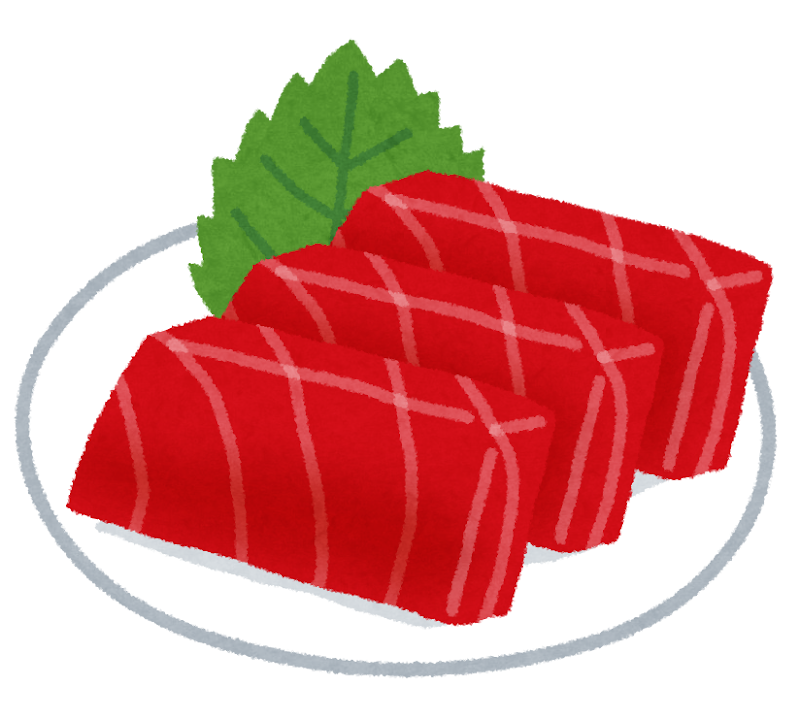
食用魚は低温下一定時間寝かせて熟成することでイノシン酸などのうま味成分が増すことが知られている。味とは別に歯ごたえなども重要な要素となる。
食感は熟成する過程において、肉身を構成する筋肉の分解の進み具合が大きく影響する。
解凍後72時間までに少なくとも三つの筋肉分解プロセスが存在することが分かった。
生魚には、必須アミノ酸、不飽和脂肪酸、DHA、脂溶性ビタミンなどの栄養素を摂取できるものの、非常に傷みやすく、腐敗の進行によっては中毒になる懸念もある。
そこで、さまざまな科学的計測法で鮮度を判定する方法がある。最近ではAIによって、魚の目の透明度や色の変化を学習させて判定する方法などもあるが、単に活け締め後の経過時間を鮮度として「学習」させているような場合は、科学的根拠が不十分であることも少なくない。
魚肉は主に筋肉で構成されているため、活け締め後の時間経過に伴う筋肉の分解が食感に大きく関わっている。そこで、SHG法によって、「食べごろ」を判定する方法が考え出されたそうだ。
表面SHG法(SHG: second-harmonic generation)
2次の非線形光学効果を利用して表面(界面)の情報を選択的に感度良く取り出すことを目的とするレーザーを用いた表面計測法
手順は、-80℃で冷凍したマグロを、実験の前日に-30℃の冷凍庫に移す。実験当日に4℃の食塩水で20秒間すすぎ、4℃で30分間保管したものを「解凍後0時間」とし、その後4℃で72時間までチルド冷蔵する。
24時間から48時間にかけて、筋肉の繊維構造が崩れ出している。72時間経つとコラーゲン繊維のみが残ることになる。これは72時間経つとサルコメア構造が失われていることを示している。
サルコメア
筋肉の収縮の最小単位である構造で、筋節とも呼ばれます。サルコメアは、太いフィラメント(ミオシンフィラメント)と細いフィラメント(アクチンフィラメント)が規則的に並んだ構造で、筋肉の収縮時にこれらのフィラメントが滑り合うことで筋肉が動きます。
12時間までは変化がないが、12時間後から24時間後にかけて筋繊維の分解が進み、コラーゲンの含有比率が増加する。72時間経つと筋繊維がほぼなくなっている。
結論は、解凍後24~48時間が、柔らかい歯応えとうま味を安定して感じられる食べごろだといえる。48~72時間になると筋肉分解が進みコラーゲンの食感を強く感じるようになる。いわゆる「筋張った食感」。
実際には「48時間」前後がうまみ成分であるイノシン酸が飽和になるので、最もおいしい食べごろだということになった。
実験は冷凍のキハダマグロなので、マグロの種類や近海物で冷凍していない場合の計測時間は異なっているが、釣ってすぐが一番おいしいわけでもないようだ。これは肉でもいわれていること。また、アジやイワシのような白身魚は、マグロとは異なっているだろうので、そこも知りたい。
上記は「理化学研究所」の学術的なレポートから平易な部分だけを抽出してみたけれど、レポートの趣旨は光学処理によるものであるので非接触で鮮度が判定できる点が画期という内容です。

