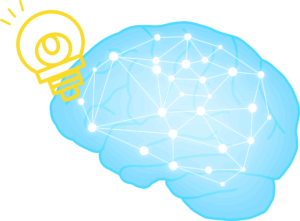マルチタスクの生産性

マルチタスク
生産性の低下 マルチタスクを行う際、脳は複数のタスクを同時に処理するのではなく、迅速に切り替えることで対応しています。 この切り替えには時間とエネルギーがかかり、結果的に生産性が低下します。 複数のタスクを同時に行うと、タスクごとに切り替えが頻繁に発生し、そのたびに注意力が分散されるため、全体的な効率が下がります。
コンピュータを相手にしている限り、マルチタスクは合理的に見えるのは、人間がコンピュータに対して余に処理や指示が遅いからに過ぎない。
タスクをマルチに処理するためにはメモリやCPUといった資源を最適化しながら切り分けて配分していかなければならない。そのための管理にもエネルギーと資源を取られる。
人間の脳
脳は過剰に働き、ストレスホルモンが分泌される。 この結果、心理的な疲労が蓄積され、最終的には集中力や判断力が低下する。
人間の脳はマルチタスクをこなしているような場合は、同時に複数の作業の処理をしているのではなく、一つ一つの作業を高速で切り替えて行っているのであって、同時に複数の処理が進行しているわけではなさそうだ。
ただ、有能な人のインタビューなどを見ていると、「考えながらしゃべらない」で「考えつくしてからしゃべる」人が多い。なまじに、頭の回転が速いことを自認している人に多いのが「考えながらしゃべる」人。
「考えつくしてからしゃべる人」は、しゃべる順番も整列されていて、話がそれても、元に戻り、そこから継続して自分の意見を言える。つまり、無駄もなく逸脱や思いつきも少ない。
しかし、これとてマルチタスクではなく、単に処理速度が速いのと導き出した答えに紐づくインデックスがきちんとしているということ。これは「生来の能力」なのか「訓練」なのかはわからないが、訓練するべき「話術」であることは間違いがない。
ツェッテルカステン
メモ術。アイデアをメモにして、相互にリンクを張っていく。
そもそもは「紙」のメモであったが、昨今はデジタルツールを駆使して相互リンクを張るなどして有機的に結びつき、思考の深化や創造的な洞察を促進するといういい話。
とはいえ、いちいちメモを書くことを継続することができるのか?
そのメモを相互リンクするのにかける時間を捻出できるのか?
一にも二にも、継続できるのか?
蓄積から価値を引き出せるのか?
と考えると、まず自分向きなメモ術ではないことは、着手前から分かってしまっている。
結論
シングルタスクで、アナログで、覚えるより忘れるほうが早くて、創造するより破壊する方が多く、メモなどしてもどこに書いたかわからなくなる方が多く、前向きに取り組む意欲もない場合は、「無気力」を共にするのが、一番自分らしいように思う。
マインドマップなんてのもかつて騒がれたけれど、メモ術で何かが変わるようにも思えない。そもそも、メモを書かなければメモにならないし、メモを書いても体系的に整理できなければ使い道がない。
そうなると「ノート術」になるが、そのノートだってどこに書いたか分からなくなるし、検索もできない。
となると、パソコンの出番だったのが最近ではスマホになった。
みんなが朝から晩までスマホを使うようになったけれど、みんながマルチタスクでメモ術やっているようにも思えない。
結局、人間は歩くのが一番良くて、思考もタスクも歩行速度を基準に生きるのが人間らしい生き方を維持できるように思う。