ワイルドカード
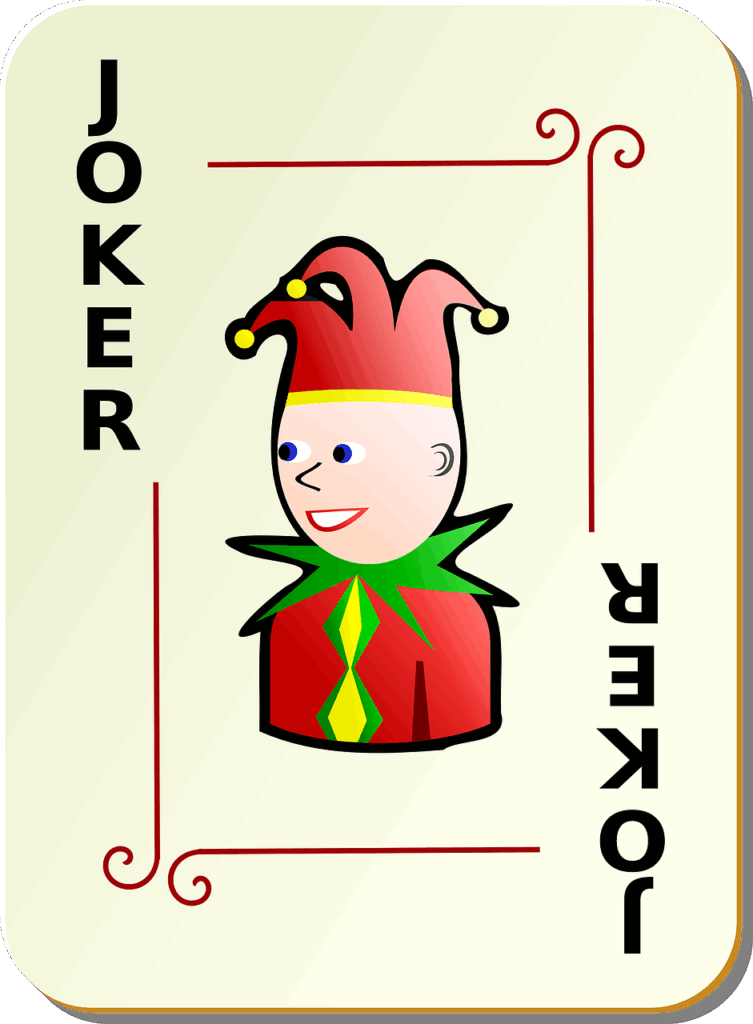
ワイルドカード
なぜ、トランプで何にでもつかるカードを「ワイルド」としたのでしょうか?「Versatile」などのほうがいいように思いますが
確かに、「Versatile」(多才な、用途の広い)という言葉も、トランプの何にでも使えるカードを表すのに理にかなっているように思えますね。しかし、「Wild」という言葉が選ばれた背景には、いくつかのニュアンスや歴史的な経緯が考えられます。
「Wild」が選ばれた理由として考えられる点:
- 予測不能な、制御不能な性質: 「Wild」には、「野生の」「制御されていない」「予測できない」といった意味合いがあります。何にでもなれるワイルドカードは、ゲームの展開を予期せぬ方向に変える可能性を秘めており、ある意味で「制御不能」な要素と言えます。この予測不能な性質が、「Wild」という言葉の持つイメージと合致したのではないでしょうか。
- ゲームにおける興奮や意外性: ワイルドカードの登場は、ゲームに大きな変化や興奮をもたらします。思わぬ役を作ったり、ピンチを脱したりする起爆剤となることがあります。この「劇的な変化」や「意外性」といったニュアンスも、「Wild」という言葉が持つ、ややもすると「荒々しい」「奔放な」イメージと結びついたのかもしれません。
- 既存の慣用表現との関連性: 英語には "go wild"(興奮する、熱狂する)、"wild card"(予想外の人物、伏兵)といった表現があります。これらの表現が持つ「既存の枠にとらわれない」「予測できない力を持つ」といったイメージが、トランプの特別なカードにも適用されやすかった可能性があります。
- 簡潔さとインパクト: 「Wild」は一語で、その意味するところが比較的直接的に伝わります。「Versatile」よりも短く、口に出したときのインパクトも強いかもしれません。ゲームというエンターテイメントの要素を考えると、簡潔で覚えやすい言葉が好まれた可能性もあります。
「Versatile」が選ばれなかった理由として考えられる点:
- やや抽象的な印象: 「Versatile」は「多才な」「用途の広い」という意味で、機能的な側面を強く表します。ワイルドカードの持つ、ゲームの流れを大きく変えるような、ある種の「爆発力」や「予測不能性」といったニュアンスは、少し弱いかもしれません。
- 日常会話での使用頻度: 「Wild」の方が、「Versatile」よりも日常会話でより頻繁に使われる単語かもしれません。ゲームという比較的ポピュラーな文化においては、より親しみやすい言葉が選ばれる傾向があるかもしれません。
最終的にどちらの言葉が適切かは主観的な判断にもよりますが、「Wild」が持つ予測不能さ、ゲームを動かす力強さ、そして既存の英語表現との関連性などが、この特別なカードを指す言葉として選ばれた理由として考えられます。また、一度定着した言葉は、その簡潔さや慣れ親しんだ響きから、なかなか別の言葉に置き換わりにくいという側面もあるでしょう。
一度定着した政党
今の政治を見ても、何が良くて自公が政権を担っているのか不思議な現象でもある。有権者という愚か者の数に頼る民主主義という仕組みに大いなる瑕疵があることは戦後80年の政治を見れば明らかだ。
政治が愚かだから官僚が跋扈することになる。
明治維新で薩長の下級武士が京都の公家連れて江戸にきた。一時は「太政官制」のような復古調を推し進めていたことからしても、近代化は彼らのなかには発想としてなかった。
それを支えたのは幕臣(官僚)たちだったと思われる。まず、軍隊が近代化し、その組織形態が官僚機構にも当てはまり、太平洋戦争で敗戦して立ち上げれなくしようとしたものの朝鮮戦争で特需が起きて、そのまま軍隊式ヒエラルキーと終身雇用・年功序列のまま、今に至っている。
能力とはほぼ無関係な「終身雇用・年功序列」は、日本人の民族性(調和とか絆という逃げ口上)、特に「妬む」気質において平穏な組織として機能してきたが、能力のある人材が成果を求めるようになると、維持しずらくなってきている。
そこで雨後の筍のように「ジョブ型」が叫ばれるようになってきたが、組織形態だけ変えてもうまく機能するはずはない。
なぜなら、率先して変わらなければならないのは経営陣であり敬遠幹部なのだから。政治家含めて、「爺」と「婆」は退場しなければ何も変わらない。
「後期高齢者」という言葉があるように、その年齢になれば一線を退くことができない社会に「ジョブ型」など笑止なことだ。
