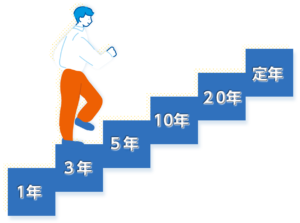「枕草子」が描いた世界《其の03》
藤原定子の兄の伊周が内大臣の時に、紙の束を伊周が妹の定子に献上した。当時の紙は非常に高価なモノであり、同時に伊周は一条天皇にも紙の束を献上していた。
天皇は「史記」を書き写すことにしたと聞いて定子は醍醐天皇が編纂させた「古今和歌集」を書こうかと考えて少納言に聞いたら、「これを給ひて枕にし侍らばや」と答えたら、「さらば得よ」といって少納言にくれた。その紙の束を自宅に持ち帰り、定子の思い出を思う就くままに書いたが「いとど物覚えぬことのみぞ多かるや」と述懐している。
おそらくこの会話は994年あたりのことと思われる。定子と清少納言は「史記」と「古今和歌集」を超える、新たな創作に挑むこととなった。
「闇の中にいて、その闇を一切書かずに光明のみを記録している」のが「枕草子」ということになる。闇の暗さを全く感じさせない創作になっていることは驚嘆に値する。

本来であれば道隆の死後に伊周が氏長者となり、太政大臣、関白になれたはずであったが一条天皇の母・詮子が一条天皇に道長を強硬に推薦したことと、伊周自身が引き起こした愚行によって失脚し、後ろ盾を失った定子は心が折れ、失意のどん底に落ちていくこととなる。
その後の道長の、定子らに対する悪意の所業は筆舌に尽くしがたいほどであるが、枕草子には、そのようなことは一切触れておらず、定子と清少納言との美しい思い出を中心に当時の宮中の出来事や人間関係、貴公子たちの振る舞いが書かれているドキュメンタリーである。
定子が西暦1000年に死亡すると、定子が生んだ男児には皇統が移らずに道長の長女である彰子が生んだ男児へと移っていく。上記の系図に書いた道長の子女たちの母は倫子で、第二夫人の明子の子たちを系図には掲載していない。その話は「大鏡」に譲ることになる。
「枕草子」が傑出しているのは、文学的エッセンスもさることながら、平安時代と共に生きた人々(といっても貴族たちになる)の知性と教養が織りなすドキュメンタリーとしての面白さが特別に優れていると思うのです。
文学的エッセンスとは、表現の美しさになるが平安時代において「春」といえば「花」であることが多かったのに、清少納言は「春」を「あけぼの」という時間で示しているのは、現在に至るまでであっても創造的な書き出しになっている。
平安時代の貴族や皇族や、その周囲の人々の言語的知性の巧みさがあればこその平安文学の開花であり、明治に続く日本文学の起点になっているが、戦争に負けてからは断ち切られてしまったことは、最大の損失かもしれない。