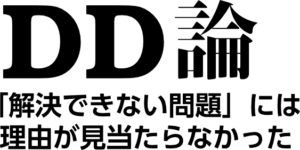限度と分際

「分際」という言葉
「分際」というと最近ではあまり使われなくなっている。最近亡くなった曽野綾子さんは「人間の分際」というタイトルで本を書いている。
辞書としては、以下のような感じ。
- 身分・地位の程度。 身のほど。 分限。 大した身分でもないのに、という 軽蔑 けいべつ の気持ちを込めて用いることが多い。「 学生の 分際 でぜいたくだ」
- それぞれに応じた程度。 ほど。 「我が―を知りて、その果報の程にふるまはば」
ここで言いたいのは「後者」。
「分」という言葉
そもそもを紐解くと「分」という言葉になる。「分(ぶん)とは、世界・社会における個々の人や物の正しい位置や取り分を指す漢語由来の言葉」となる。
人間が虚弱の存在でありながら、獣たちに対して優位を占めるのは群れて集団生活を送ることが可能であるからであり、それを維持するための原理が「分」である。
人間の間における相違を確立し、その間に「分」を与えて関係を定めて全ての人々が相違と関係を維持するための規則であるを守れば争いを起こすことが無くなって社会は安定し、より強力になるという考え。
社会においては「主僕の分」の概念が強く主張され、儒教、特に朱子学では江戸時代の武士の身分制維持に最大限利用されていた。
という長めの前置き。
40年前の経験としての分際
40年程まえ、いつも世話になっている先輩夫婦にお返しをしようとなり北川さんが3万円のワインで、自分が3万円の松坂牛を持っていくことにした。
40年前の物価で、4人で3万円の牛肉は、さすがにおいしかった。で、いよいよ、3万円のワインの登場。
で、4人が一口飲んで「知黙」。
ワインの味が分からないのか、そもそもうまくもない価格だけのワインだったのか。
というか、ワインの味など、そもそも分かる「分際」ではなかった。というか、味が分かるのに「分際」が必要なものなど欲しがる必要もないことだった。
分際と大吟醸という狂乱
それが、最近の大吟醸にも言える。5割、4割、3割、2割。馬鹿の上乗りで1割を割り込むのまで出ている。買う者も「分際」もわからずに金だけ出している。作る方も「分際」が分からないから、そのような外道の所業のようなものを作る。
酒なんて、酔えばいいだけのもの。そもそも「燗」をしてはいけない酒なんてものが既に「邪」の道に入っている。
1升2千円程度の酒で十分に酔える。
結論は、「分際」が分からないから「限度」をわきまえないということ。それが、人間社会を雑駁なものにしていくことが分かっていない世の中になった。
「分際」の役割の一つの側面として「文化」がある。古い考えと指摘されるだろうが分際をわきまえないことで文化のレベルが低下していく。