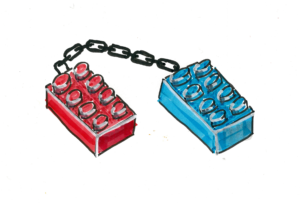順天堂と明治早々の医療

「胡蝶の夢」という本と荘子の寓話
司馬遼太郎の歴史小説に『胡蝶の夢』というのがある。黒船来航によって幕末の日本が大きく動き出す中、蘭学を学び、幕府の奥医師となった松本良順と、彼の弟子である島倉伊之助(司馬凌海)の生き様を描いた作品であるけれど、これがなぜ「胡蝶の夢」と題されたのかは不明。
荘子が言う「胡蝶の夢」とは、個人において「観念」と「実態」に本質的な差異がないとする超刺激的な考えで、これを始めて読んだ日の感激は忘れられない。
それゆえに、今でも司馬遼太郎の「胡蝶の夢」という小説と題については納得していない。
松本良純という人
松本良順は、佐倉順天堂を開設した佐藤泰然の長男として生まれた。順天堂を継がず、松本家の養子になり、蘭学を修め、幕府の奥医師となる。幕府の医学制度の改革に尽力し、また、戊辰戦争では、新政府軍の軍医として活躍した。
司馬凌海という人
伊之助(司馬凌海)は、佐渡で生まれ、13歳で奥医師松本良甫、松本良順のもとでオランダ語と医学を学ぶ。下総国印旛郡佐倉の佐藤泰然の私塾順天堂で蘭学と蘭方を学ぶ。語学の天才と言われ、独・英・蘭・仏・露・中の6か国語に通じていたという。
司馬凌海は、明治9年に公立医学所(今の名古屋大学医学部)の教授となり、教え子に後藤新平がいるが、あまり情報は多くない。
長谷川泰然という人
長谷川泰は、越後長岡藩の生まれで文久2年(1862年)江戸に出て英語、西洋医学を学び、佐倉順天堂で2代目堂主の佐藤尚中に西洋医学を学ぶ。慶応2年(1866年)、松本良順の幕府西洋医学所で外科手術を修め、戊辰戦争の勃発により、北越戦争で河井継之助に従軍するも破れ、維新後の明治2年(1869年)大学東校(今の東京大学医学部)少助教になる。
長谷川泰は、明治8年(1875年)12月27日東京府知事から済生学舎開業願が許可され、明治9年(1876年)4月本郷元町1丁目66番地(順天堂大学から水道橋方面に行った真ん中あたり)に西洋医の早期育成のための私立医学校済生学舎(後に東京医学専門学校済生学舎、日本医科大学の前身)を開校する。
日医大の創始者であるが、知名度は限りなく小さいし歴史的にもほぼほぼ無名。
野口英世は済生学舎のOB
ちなみに、済生学舎は紆余曲折を経て根津にある日本医科大学として、私立の医科大学としては日本最古の医療教育機関として現在に続いている。済生学舎の卒業生に野口英世がいる。
佐藤進と順天堂
佐倉順天堂で2代目堂主の佐藤尚中に、長谷川泰と同期で学んだ3代目堂主の佐藤進は、東京に出て佐藤順天堂病院を現在の順天堂大学病院がある場所で開業。明治2年(1869年)、明治政府発行の海外渡航免状第1号を得てドイツに留学。ベルリン大学医学部で学び、1874年(明治7年)にアジア人として初の医学士の学位を取得している。
時代を変えるには
日本の歴史では、ロシアやフランスのように人民から現状打破の動きが起きたことはない。権力機構が入れ替わることで、現状を御破算している。なんにせよ、現状を御破算にすれば再び有能な人材が活躍する時代が予定されていることは歴史が示している。
アメリカでは政府効率化省(DOGE)という役所が連邦政府の予算に介入して、批判もされているがイーロン・マスクが大活躍をしている。
このようなことができない限り、政権が交代してもかつての民主党と同じレベルからの脱却はできない。
結論は?
「胡蝶の夢」のすごさは、「夢」という「観念」と、「夢を見ている自分」という「実体(摂理)」のどちらが自分の存在なのかという「問い」をすることがすごい。
自分として同様に感心したのが、直江兼続の漢詩で「天上人間一様秋」というのがある。「天上」を「観念」とすれば「地上」は「摂理」になる。人生も黄昏てくると摂理も観念も一様になってくるという慨嘆。
この慨嘆に荘子の胡蝶の夢は通じているものがある。
しかし、司馬遼太郎の「胡蝶の夢」から順天堂を中心に書き始めた記事なのに結論がこれでは、話の辻褄があっていない。