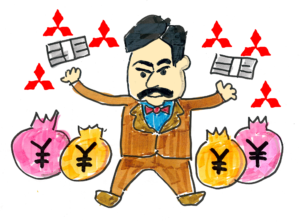「読後廃棄」と公務員の仕事の関係
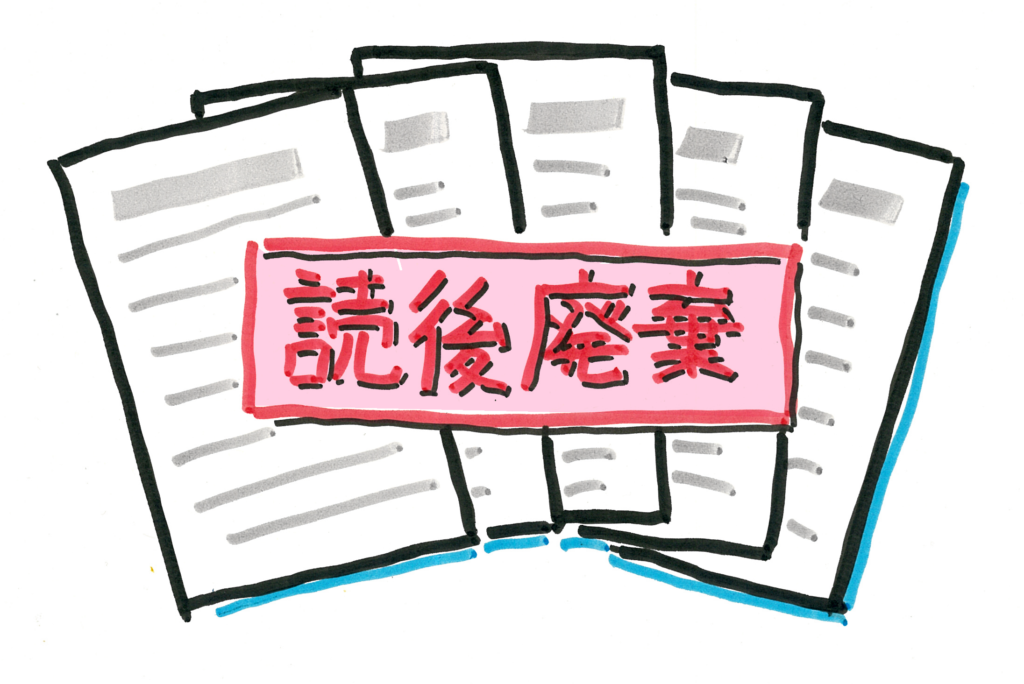
「読後廃棄」の意図するもの
山本太郎さんの追及も素晴らしいですけれど、その内容はともかく「読後廃棄」という言葉が耳に新しかったので、少し考えを述べてみます。
公文書は「情報請求」ができることを前提としています。官公庁の文書は、ほとんどが予算や執行する側の権力行使に関する文書になります。官公庁が執行する予算は、すべて「税金」で賄われています。公務員(官僚も含む)の給料も同様に税金で賄われています。彼らが利益を生んでいるわけではありません。
公務員の仕事
「公僕」などという言葉もありますが、読んで字が示すがごとくで国民に尽くすことを生業としているわけです。国家や地方自治を動かしているというような上から目線の仕事ではなく、国民のために各自の能力や専門性を生かして国民の円滑な生活に資するのが彼らの職務になります。
彼らの主要な職務は、専門的知識や知見を公平・公正・中立に生かすことで国家や地方自治に尽くすことになりますが、それには「公平・公正・中立」であることの「証拠」を残さなければなりません。
「文書主義」を調べると
wikiで「文書主義」と調べると「役人が文書を作ることを仕事にしていること」のように書かれています。これは一面の真理ではありますが、表向きには、「公平・公正・中立」に予算を執行し、「公平・公正・中立」に権力を行使したという証拠(証明)のために文書を残さねばならないのが、彼らにとっての「文書主義」になります。
そこで「読後廃棄」という言葉に戻りますが、いかなる文書であっても、公務で作成した文書であるなら公民の財産であるわけです。なぜなら彼らがメシを食えるのは納税者がいるからで、それを「読んだら棄てろ」ということは、仕事をしなかったことにすることと等しい所業になります。
アベノマスクに関する記録
悪名高い(けれどメディアが封殺したのであまり話題ならずに忘却されつつある)アベノマスクで400億円を超える無駄遣いがされた。その発注などの管理記録を公開せよと訴訟を起こしたところ、関係した官僚は全てメールでやり取りし、メールボックスがいっぱいになったから廃棄したとのことだった。
これでも、公文書管理法違反で罰則を受けた公務員は1人もいない。
所業とすれば「破廉恥」であるが、職務に付随する明らかな違法「的」行為であるゆえ「非破廉恥」として告発し、刑罰を与えさえすれば、この手の違法行為を一掃することができるが、法律を作る政治家は公務員抜きには飯も食えない。新人議員に10万円を配ることもできないから、罰則を規定することもできない。
公務員の考え方
公務員遣ると分かるけれど、上司になる「老人」達の中には、話しても分からない人たちが少なからずいる。その彼らが転勤でどこかに散ってもらうまではカシズかなければならない。
よって、無能な政治家にカシズクことくらい、日常のことなのでなんとも思っていない。
中島敦の「文字禍」
中島敦の「文字禍」という小説の中で「書かれなかったことは、起きなかったことだ」という会話がある。5年、10年の歳月の中で文書として残されていないことは、なかったことに等しいことになる。
公務員は、選挙で選ばれていないので民意を反映していない。その彼らが、自己の職務の証拠である文書を廃棄することが許されるなら、政治は不要になる。
つまり、「読後廃棄」という指定は、自らの職務に対する責任を否定するだけではなく、政治を否定しており、つまりは納税者を愚弄していることに等しい所業ということになる。
「読後廃棄」させない方策
情報公開で黒塗りにするのも結構であるが、「読後廃棄」はさせるべきではない。むしろ、「読後廃棄」させる意図は「隠蔽」しなければならない事情があるからであり、かえって、記録として残さなければならない。
そして、公開できない場合は、その理由、その決定者(政治家の名前)、何年後に公開するかを明記することが必要で、そんなマナーを民主主義というのではないでしょうか。
公開できない文書も中にはあると思います(防衛、公安、個人保護、企業秘密など)が、10年以上公開できない場合は、せめて首長(国なら担当大臣と総理大臣)の裁可と理由と、そして10年ごとの見直しなどを義務付けるべきでしょう。