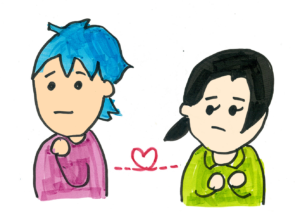「インタビュー」という難しさ
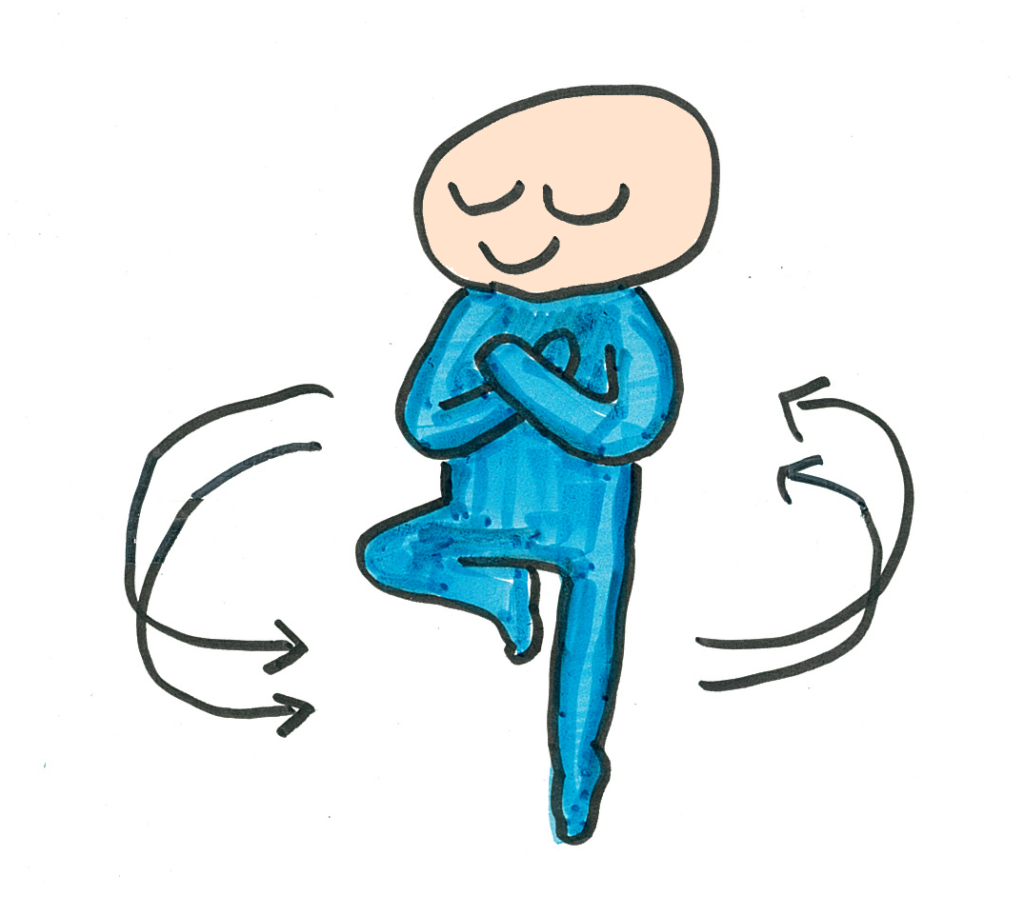
政治であれ経済であれ金融であれ、あるいは学問の世界であれ、医学であれ、その世界でそれなりの実績を上げている人、努力をしている人にインタビューをする場合、それらの人々が描いている世界観を、それらの人々なりにしゃべらせるだけではインタビューとしては平板なものになってしまう。
それらの世界観を持った人々に、切れ込むことで彼らが常日頃考えてもいないような新たな世界観を引出せるような、そのようなインタビューであればこそ、聞き手の腕の見せ所にもなる。
石丸伸二の開票速報のような、およそ聞く意味のないことを聞くだけで尺を埋めるようなインタビューなどが、つまらないインタビューの最たるものになる。そこに、そのインタビュアーがいてこそ成立するような聞き取りが丁々発止のだいご味になるはず。
そんな点で、PIVOTの佐々木さんの、石丸伸二さんに対するインタビューは素晴らしいと思った。せめて、テレビの報道は、最低でもこのレベルであってほしいのに、全く努力と能力が足りていないことを、石丸伸二さんが露呈させたことには大いなる意味があった。
ホリエモンのロボット博士へのインタビューで「ウォホホホ!ヤバ!!こいつスゲーな!」では、インタビューが成立しているとは思えないし、ロボット博士の世界に踏み込めていない。
PIVOTの佐々木さんは、石丸伸二さんの世界にインタビュアーとしては十分踏み込んでいると言える。日本では有名になると、それだけでプロフェッショナルとして起用されがちである。それは、「有名」ということと「場慣れ」だけのプロフェッショナルであって、プロとして活躍している人の世界へ踏み込むためには、インタビュアーが、インタビューする人の世界へ踏み込むだけの力量を持ったプロフェッショナルでなければ、話を立体的にすることは出来ない。
それと、石丸伸二さんを「テーゼ」とすると、必ず「アンチテーゼ」が登場する。そのそれぞれにおいて、他の立脚点や思索を想起しようとすることで、自己の思考のレベルを上げられると言っていた人がいた。
それこそが、小池百合子さんが唱えた「アウフヘーベン」の本義である。対立から生まれる思考価値より、はるかに大きな価値を手にすることができる。それが、日常における、庶民にとっての「哲学」の実践だ。
メディアが低劣になってしまったのは、制作側の人間が大衆を「睥睨」していることによる。しかも、睥睨する根拠は能力でも度量でもなく、メディアとしての権力だけだ。
「迎合」でも「啓蒙」でもなく、視聴者を子馬鹿にし、その傍らで権力にはおもねるという最低の人種がメディアの制作側にいることに大きな原因がある。