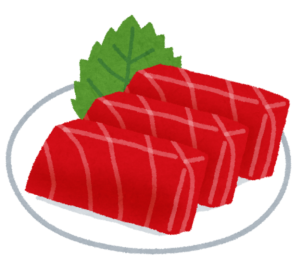「創造」と「獲得」を結びつける

1980年代の日本は「技術大国」だった。そこでアメリカは、
・イノベーション創出(研究開発〈R&D〉資源の最適化)
・技術と経営の融合(技術とビジネス戦略の統合)
と、この2つで日本を叩き潰そうとした。このことを良く分析すると、「製品開発」や「品質向上」にマネージャは専心しているが、イノベーションに専心するマネージャが手薄であることを見抜いた。
ほぼ、唯一の例外がトヨタだった。トヨタのチーフエンジニアは、製品開発だけでなく、開発(価値創造)からマーケティング(価値獲得)に至る全てのプロセスに責任を持つことで、価値の創造主の役割を担っていた。
MOT(技術経営:Management of Technology)という考え方があるそうだ。「種」を見つけて「研究」する。市場を見て「開発」し、「事業化」する。市場規模を拡大して「産業化」する。
とはいえ、そう簡単に事業化や産業化ができるわけではない。
「研究」から「開発」のあいだには、技術の実用化に必要な資金調達、研究者と事業化担当者の考え方の違い、基礎研究と実用化研究の方向性の違いなどが立ちふさがる。
「製品開発」から「事業化」のあいだには、大規模な設備投資の必要性、市場ニードとの適合性の確保、量産化技術の確立、初期投資回収までの資金繰りなどが立ちふさがる。
「事業化」から「産業化」のあいだには、競合他社との差別化、市場シェアの獲得、継続的な製品改良、ビジネスモデルの確立、顧客基盤の構築などといった問題が立ちふさがる。
「シード(種)」からスタートするのか、「ニード(要望)」からスタートするのかでいうなら、「ニード」には市場からの要望があるだけ苦労は少ないが「iPhone」は生まれない。
また、アイデアがいかに面白くても、利益を生み出さなければ企業価値としては「無」か「負」である。それが、いかに素晴らしい歌手であっても、売れなければ企業価値を創造できないし、逆に、歌なんてどれだけ下手であっても売れれば企業価値を最大化できる。
つまり、売れるか売れないかの価値基準として創造側と消費側に乖離があることは少なくない。「部分最適」だけでは、市場開拓ができないことになる。
ジョブスはiPhoneを創造しただけでなく「Apple Store」や「App Store」も創造している。
つまり、「創造」と「獲得」が、見事に結合している。
最大の課題は「作る側」からの発想からスタートするのか、「売る側」からの発想からスタートするのかのバランス(調整)が、部分最適企業においては難しいことになることである。
ともすれば「テーゼ」と「アンチテーゼ」の関係に陥りやすので、「アウフヘーベン」の役割を担うリーダーシップが求められ、そうした人材によってブレークスルーが可能になっていく。
リーダーに与えられている権限は、「リスク」を最小化させるために能力を最大化することにある。日本の巨大企業の経営幹部は、リスクを最小化するための方便として権限(決定)を行使しないことになっていく。
仮に凡愚(1人称で使っているので「私」ということ)が財務省の事務次官になっても東京都知事になっても、余計な口出しさえしなければ4年くらいはつつがなく財務省も東京都政も動くであろう。こういう組織構成であるがゆえに30年停滞してしまったわけで、大組織や官僚組織は、上に行くほどに何もしなくなっていく。
管理職には権限を持たせる以上、その権限は責任と裏腹でなければ単なる利権と化していく。責任とは組織にとって有効と思われる判断に付随するものであって、判断にはリスクが付きまとうが、それゆえに組織が成長できることにつながる。リスク回避のために判断をしなくなることから退廃がはじまる。
フジテレビの茶番は、日本の大方の大規模組織の縮図として学ぶべきことは多い。