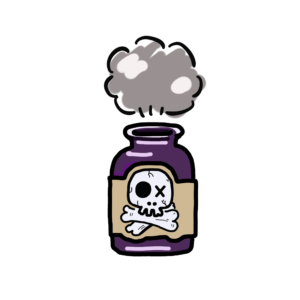「プレイブック」とは?

マニュアルとの違い
【問い】マニュアルとプレイブックは、何が根本的に違いますか?
マニュアルとプレイブックは、どちらも業務遂行のための指針を示すものですが、その目的や対象、内容に根本的な違いがあります。
マニュアル
目的: 業務の手順や方法を標準化し、誰でも同じ品質で業務を遂行できるようにすること
対象: 業務の初心者や経験の浅い人
内容:業務の基本的な手順やルール、ツールの使い方や操作方法・トラブルシューティングの方法、注意事項や禁止事項
プレイブック
目的: 経験豊富な従業員の知識やノウハウを共有し、チーム全体のパフォーマンスを向上させること
対象: 業務に精通した従業員やチーム全体
内容:成功事例やベストプラクティス、具体的な戦略や戦術、状況に応じた対応方法、チームの役割分担や連携方法
主な違い
マニュアルは「手順書」、プレイブックは「戦略書」
マニュアルは「標準化」、プレイブックは「最適化」
マニュアルは「初心者向け」、プレイブックは「経験者向け」
営業部門の場合
マニュアル: 顧客管理システムの使い方、見積書作成の手順
プレイブック: 顧客との関係構築の方法、競合他社との差別化戦略
IT部門の場合
マニュアル:ソフトウェアインストール手順、アカウント作成手順
プレイブック:システム障害発生時の対応手順、データ復旧手順
つまり、マニュアルは業務の「基本」を教えるものであり、プレイブックは業務の「応用」を教えるものと言えるでしょう。
↑ ここまでは「gemini」の回答。以下は、ネットをググったら長文の解説があったので、それを参考にしてみた。
プレイブックの定義
営業プレイブックとは、企業の営業活動全般に関わるあらゆる情報を体系的にまとめた資料のこと。営業戦略、顧客ターゲティング、営業プロセス、トークスクリプト、行動指針、KPI、営業ツール、成功事例などを網羅し、営業担当者が営業活動を行う上での指針となるものの総称のようだ。
役割
営業活動の効率化と標準化を通じて、企業の収益拡大に貢献することだそうだが、そんなに簡単に貢献できれば世話はない。
プレイブックに記載されたプロセスに従うことで、トップパフォーマーと同等の成果を上げられる可能性を秘めているようなので、ドジャースにプレイブックがあれば、みんな「大谷」になれそうだ。
成果の可視化を促進
これって、大昔からやっていると思う。棒グラフとかで、誰が一番売ったかを見えるかして、競争させていた。
属人的な営業スキルに頼らず、再現性のある成功プロセスを持つことで企業の競争力を高めるとのこと。
難しい言葉の羅列
データドリブン、CRM、SFA、目標管理、コミュニケーション、リーダーシップ、KPI等々。
こうなると、プレイブックはちょっと厄介な気もしてくる。
geminiでは
マニュアルは業務の「基本」を教えるものであり、プレイブックは業務の「応用」としており、大元はアメリカンフットボールで使用される作戦ノートに由来しているようだ。
試合に勝つための実績やノウハウを活用してセオリーを導き出す手戦略集。
まず、プレイヤーに能力があることが前提となる。同時に、勝つための売るもの、つまり「アスピリン」がなければ、宣伝詐欺に近似する。
あとは、「効率」と「競争」。ここにおいて、リーダー次第によって、あるべき戦略書として十全に機能する可能性を持つ。
まとめ
とはいえ、職務マニュアルすら整備されていない職場において、いきなり「プレイブック」というのもありえそうな話ではない。
戦後、80年経っても、いまだに終身雇用&年功序列の属人管理をしている企業において、人材流動化やJOB型雇用が浸透しだせば、まず、どこの企業も不要(無用)な中間管理層の削減が必須になる。
アメリカではIT企業から、人材の入れ替えが激烈になりAI人材の取り合いになっている。
日本でも、そんな取り組みが増えるのだろうけれど、なにをしたところで少子高齢化の波が、消費社会を襲う。