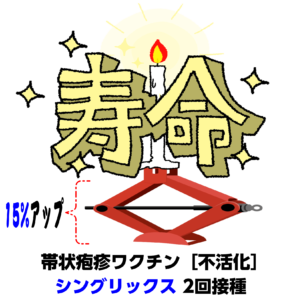組織の生産性と個人の能力
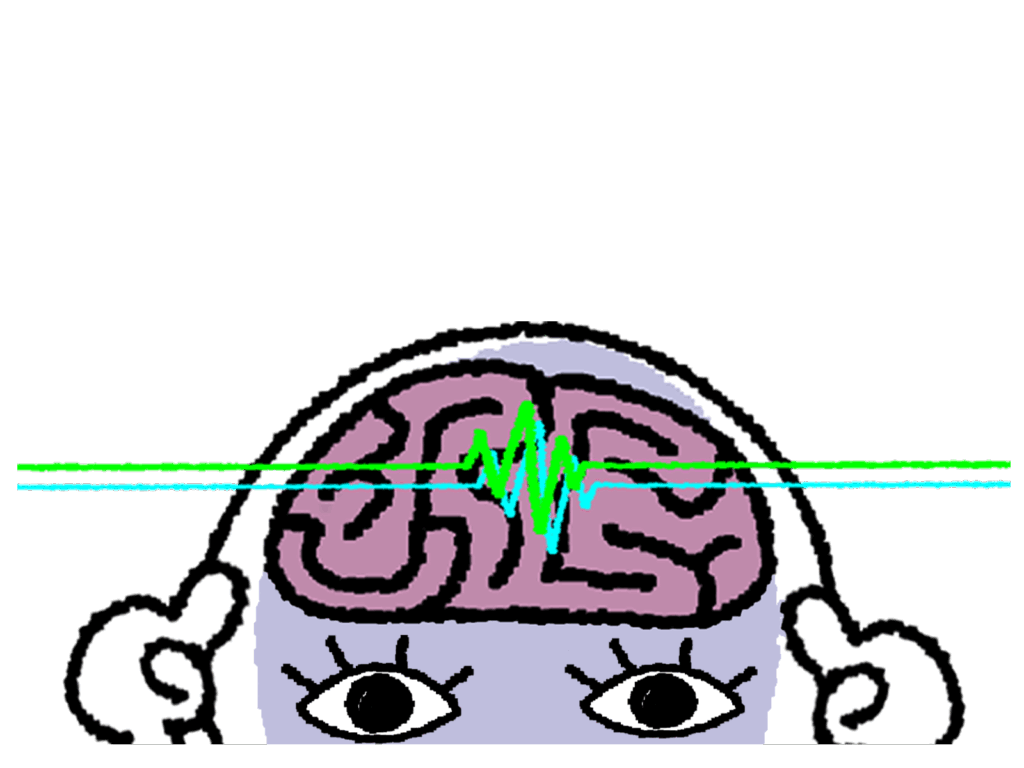
能力の総和
要するに「優秀」「有能」「スタープレーヤー」を集めれば、能力の総和で考えもしないような結果を生み出すのではないかと思うけれど、実際にはそうならないということになる。
最高幹部だけを集めたグループは合意に達しないことが多いそうだ。最高幹部だけのチームは64%が結論を出せずに終わった。なぜなら、議論に集中せず、権力争いのほうに忙しかったからだ。力関係によっては妥協も難しくなる。
協調か対立か
序列における自らの位置を認識しているか否かが影響している。それぞれの相対的地位について共通認識があれば、チーム内で権力争いは起きにくく、生産性は高くなる傾向があったが、地位の高い個人だけで構成されるグループで、互いの上下関係が明らかではないと、ヒエラルキーの上層部ほど、人々は激しい対立を始める。
「知性の罠」
というのが、記事の主張であり、そのもととなっている「知性の罠」という本の主張である。
図書館にあったので予約を入れて置いたが、著者がアメリカ人のようでもあり、あまり期待はできない。
しかし、それはアメリカなどでの「有能」とされる人材を集め、その挿話でさらなる達成を望もうとすれば、協調より対立が生まれそうな感じがする。翻って日本の組織ではどうだろうかと考えてみる。
日本型有能とは「忖度」
フジテレビを参考にする限り、巨大企業だからと言って、経営幹部は「優秀」「有能」でなくてもなれそうである。日本の組織において、一番重要な能力とは「忖度」である。よって、忖度されるメンバーはそっくり返っていればいい。忖度するメンバーは、対立してまでシノギヲ削る必要もない。
リスクが少ない代わりに、生産性への寄与も少ない。主体的に「決断」したり「改革」したりしなければいい。役に立っているふりをしながら、人柄の良さを前面に出してさえいればいい。
そうこうしているうちに、半導体、テレビ、家電などが消えていった。
大日本帝国軍隊の参謀
その典型的な例が大日本帝国軍隊だと言える。陸軍大学を優等で卒業したわずかな人材が「参謀」となり、作戦を立て軍を支配した結果が「あれ」だった。その構造が、そのまま現代にも生きているのが官僚であり、財務省である。
ノモンハンで大失敗した参謀をインパール作戦で起用して大失敗している。
彼等は、国家とか国民とかのために「起案」しているのではなく、己の優秀さを文字にするのが、彼等の起案であって、仕事は自己の優秀さ、有能さの表出の場でしかない。
官僚主導で、戦後80年の結果が現在になっている。それでも、いまだに政権与党の多くの議員は官僚に額づいて官僚主導の政権運営に神輿として担ぎ上げられて携わっている。