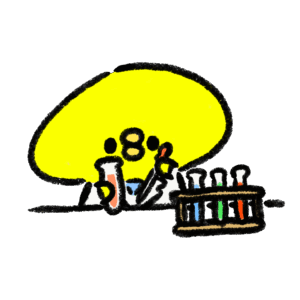「再生の道」とは

「再生の道」は何を再生するのか
石丸伸二さんが作った政党である「再生の道」で、都議選と参院選を戦うとのこと。
都議選では1000人から面接やらペーパーテストやらで都議として「優秀」と思われる人材を選出していた。それで、各候補が決まったようで、一部には辞退者も出ている。
その理由はさまざまあるでしょう。
立候補する人材がどれだけ優秀であっても、決めるのは有権者であって、都知事選見ればわかるように、開票と同時に小池百合子さんが300万票を獲得しているのが、東京の選挙。
立候補している人材が、どれだけ優秀であっても、あるいは、逆に優秀だからこそ「入れない」というアンチも少なからずいるわけで、優秀だから都政を「再生」してくれることには直結しているわけではない。
そもそも現状の都政に「再生」を望んでいる層がどれだけいるのかも不明。
国政政党・再生の道は「教育投資」
国制政党の政策は、いきなり「教育投資」だそうだけれど、都議選の立候補者から参院選の候補者として選出されたメンバーで、そんなに教育投資に情熱をかけていた人がいたとは思えなかった。
今どきの国政選挙の争点としては「ぬるい」感じが否めない。
「政治再建」:政治の質を上げるための施策を明示する
「天下り根絶」:どれだけの予算が無座に使われているかを示す
「未来投資」:ここに教員と教育の仕組みを入れ替えるくらいのを持ってくる
官僚機構と予算の適正化から政治再建を目指すような、もっと響きのあるテーマとするべきだったように思う。教育投資をするためには文科省の解体的出直しや、各自治体に根を張っている教育行政の改革は避けて通れない。
教員の持ち時間を少し楽にしてあげたからと言って教育効果として何が得られているのかデータがない。得られたデータは使った予算額だけ。
言わんとすることはわかる
「言わん」とすること、「やらん」とすることはわかるが、石丸さんの思考力の範囲と、集めた優秀なメンバーらの思考力を結集したところで、民主主義という「低効率」「低理解力」の総体に対して、どれだけの「再生力」を持つかというと、はなはだおぼつかない気がする。
政治とは、結局は「エンターテイメント」などにはならず、「愚鈍」で「不純」で「無為」で「無駄」なものでしかないが、民主主義を前提にすると、これを超える仕組みにはならないということのようだ。
ようするに「民度」において決するのが「政治」であるということ。トランプ(プーチン、ネタニヤフとかも)のようなリーダーがいきなり登場して、国民の支持をいいことに好き勝手をすることも、一つの民度による仕組みではあるが、これとて「無為」においては日本の総理大臣や閣僚らとほぼ等価であるといえる。
「聖人君子」「優秀」「有能」「海外経験」「高学歴」等々集めたところで、とどのつまりは「プロジェクションマッピング」「お台場噴水」「外苑樹木伐採再開発」を着々と進行しているのが「政治」の現実で、それを愚かなこととして「再生」すれば何がどのように変わるのかのアピールが本来は政党の「政策」のはずのような気がする。
「是々非々」とはいうものの、有権者にとっての「響」が必要で、あとのことは選挙に勝ってから考えればいい。かなりの有権者のレベルにあわせるのが、選挙の「エンターテイメント性」であって、政治の「エンターテイメント」とは切り分けるべきだと思う。
今のところを客観的(はなはだ主観的であるが)に眺めてみる限り、政治とは、石丸伸二さんにとっての「エンターテイメント」であることは間違いのないところのようだ。