Novell社の「NetWare」を思い出した
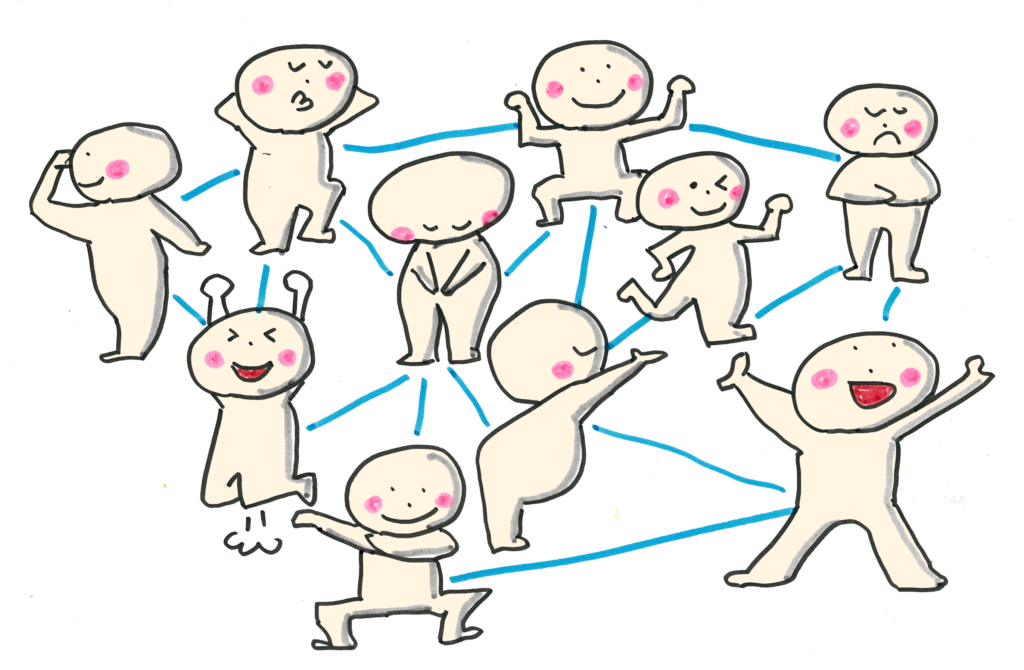
NetWare
パソコンの黎明期にNetWareというLANのソフトがありました。作ったのはNovell社でした。NetWareが世に出たのが1983年と言います。いまから40年ほど前のことになります。
Novell社はイーサネットカードの製造会社を買収し、Novell社の存在を強固にした。1990年までは、Novell社は独占的な地位を築いた。
1995年あたりからWindows3.1、OS/2、LinuxなどのOSにはネットワーク機能が標準で含まれるようになって、Novell社は急落していった。1997年にGoogleのシュミットがNovell社のCEOになっていた。
1999年までにはNovell社は支配的にポジションを失ってい、2000年になるとPC向けネットワークサーバーの市場はWindows 2000 Serverに奪われた。
というのが、パソコンのLANの黎明期の話です。
アクセス権限
そこで思い出すのが、NetWareです。ユーザーの権限管理や「継承」というような機能があって、ファイルサーバーに対するアクセス権限を非常に細かく設定できました。設定のレベルはDECのVAXライクな感じでした。
ちなみに、WindowsのOSも、DECから引き抜いた技術者が作ったWindows NTがベースになっている。余談であるが、VAXのOSの名前が「VMS」であった。Windows NTは「WNT」で、アルファベットで1文字ずつ先の文字になっていた。つまり、VAXの一歩先を行くという意味であるという風説もありました。
管理とは性悪説
話をNetWeraに戻すと、ネットワークの管理の前提として「性悪説」に立っていたとも言えそうです。というか、ここがそもそもアメリカと日本の「管理」の視点の根本的な違いと言えます。
NetWareでのネットユーザーやファイルサーバーの管理は、マイクロソフトのようなルーズなものではありませんでした。
性善説とはルーズ
それに比べてマイクロソフトのネットワークは、いい言い方をするなら「性善説」に立っていたと言えるでしょう。違う言い方をするなら「ルーズ」。だから、誰にでも使えました。
いまでは、あえて「LAN(Local Area Network)」ということもなくなり、ハブにケーブルをつなげば、いとも簡単に世界に接続できるようになりました。
人材が流動化するようになると、ネットワークのみならず「管理」の原点は「性悪説」に立たなければならなくなるでしょう。
管理職という無能
昇進して止まった階級においてヒトは「無能」になるのだ。そして、無能な管理職として欧米では「レイオフ」、つまり解雇の対象となる。
無能とされないためには「管理」能力を発揮しなければならかったが、いまとなれば「管理」はAIがやる。
となれば何が求められるかと言えば「知識」「知能」「発想」「創造」「経験」。
組織の行き詰まりを打開できるような「突破」とリーダーとしての「カリスマ」が無い限り、組織で生きていくことが難しくなる時代が来つつある。

