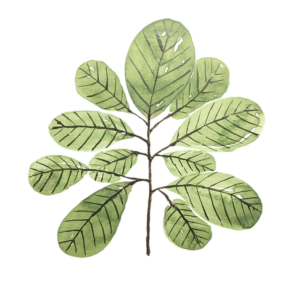尾崎放哉の生きざま、死にざま
吉村昭が書いた「海も暮れきる」を読みました。人間が朽ち果て、死んでいくところをここまで鮮烈に描いた小説は数少ないと思います。
テレビや映画で、主人公が死ぬときは、お涙頂戴を語るだけ語ってから、やおら死ぬというのが定番ですが、うちの義母は衰弱しご飯も食べられなくなり、最後には水も飲めなくなって意識も混濁し、そのうち意識もなくなってから、そして最後に死んでいきました。死因は老衰。
尾崎の死因は「癒着性肋膜炎湿性咽喉カタル」だそうですが、小説によれば結核が喉にうつって飲み食いができなくなり、下痢と便秘を繰り返し、衰弱し、最後には糞小便ができなくなったのを、無償で世話をしてくれた農婦とその旦那が最後まで世話をしてくれているのが救いでした。
どんなに落ちぶれても住む家は必要だし、飯も食わなければならない。しかし、お金が稼げなければ、死ぬか、施しを受けるか、悪事を働くか しかないわけで、尾崎はみじめになるほどに施しを受け続けた挙句に死にました。
何か求むる心海へ放つ
帝国大学をでて、エリートの道を生きるはずだったのに、酒癖と人柄が悪くて破綻し、寺男などをしながら流浪の果てに海が好きで、小豆島にたどり着き、そこの地で朽ち果てて死ぬ人生に、共感するものはきっとない。
やせたからだを窓に置き船の汽笛
生活保護や、医療制度などにより、放哉のような「朽ち果て死」は望まなければあり得ないご時世ではあるけれど、結局は意識が混濁してくれば管に繋がれて糞小便を垂れ流して医療関係者の世話になりながら死ぬか、最近はやりの家族に面倒掛けながら死んでいくには変わりはない。
病を得て死ぬ、あるいは老衰で死ぬとしても、正常な生活から死に至る間は、動物としては店じまいなだけでどうということもない摂理の輪廻でしかない。「死」をことさら尊大にとらえているのは「思惟」でしかない。
障子あけて置く海も暮れきる
海が好きだったことの一つには、海に入ればいつでも死ねるということでもあったが、衰弱すれば海にまでもたどり着くことはできない。
なぜ、吉村昭がここまで、尾崎の死に行く姿を描いたかといえば、吉村自身も若かりし頃、結核によって死を覚悟することがあったと後記に記している。その時に読んだ本は尾崎放哉の句集だけだったとか。尾崎の死をみつめることで、人の死を書く重さを見つめることにもなっている。
そのリアリティはすさまじく、そして海が死を受け入れてくれることはなく、死こそが誰にとっても全てのことからの解放なのであると感じさせられた。
トルストイの「イワン・イリッチの死」でも、下男のゲラーシムが嫌がる風もなく下の世話をしてくれるたことは、放哉の世話を無償でしてくれた夫婦にも通じる救いがあった。