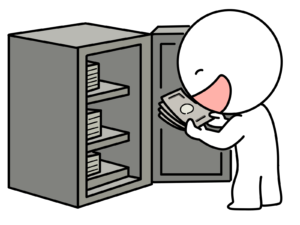荘子を考える:斉物論《其の06》
「斉物論」とは、「物を斉しくする」という意味で「彼此是非」の差別観を超えて万物斉一の理を明らかにする。
「逍遥遊」で自由無碍の境地を推奨した。次なる「斉物論」により「物を斉しくする」という考えを打ち出す。「物を斉しくする」ということは一切の存在は、究極的に「一」であるという考えに至ることである。ここにおいて人間の心は「逍遥」に遊ぶことができるようになる。それを明らかにするのが「斉物論」である。
師である南郭子綦と弟子の顔成子游の会話で話が進む。
子游曰:子游曰わく、
地籟則衆竅是已:地籟は則ち衆竅(もろもろの穴)これのみ
人籟則比竹是已:人籟は則ち比竹(笙や笛)これのみ
敢問天籟:敢えて天籟を問う と
子綦曰:子綦曰わく
夫天籟者吹萬不同:夫れ天籟のものが吹くこと万にして同じからざれども、
而使其自己也:而も其れをして己に自わしむ
咸其自取:咸く其れ自ずから取るなり
怒者其誰邪:怒たてしむる者は、其れ誰ぞや と
「籟」とは、「響き」のこと。「人籟」は人が楽器を奏でる音であり、「地籟」は大地が発する響き、すなわち風が木々や地面の凹凸をすり抜ける際に起こる風の音のこと。風が起こり、風が止む。風が止むと静寂が戻る(この間の描写は、ことに文学的に秀逸であると言われている)。
風が吹けば地面が音を立てて鳴くのは、諸々の穴があるからだ。人が吹く笛は竹でできている。では、天の笛とはなんなのか と問うと、地の笛も人の笛もみな違うように聞こえるが、風に対して自らが音を立てていると言うことは同じである。音色は風が選んでいるのではなく自ら自身で音が選ばれている。そうすると、風に呼応する音を出しているのは何なのだろうか?
事物の結果を因果に結び付けて考えることで人間を思惟で縛ることになる。現象はそのこと自身で起きていると考えれば「因果的思惟」などにとらわれる必要は一切なくなる。
「天籟」とは、音を立てているすべてのものが自己自身の原理によって響きとなるだけのことにほかならない。ここでいう「天」とは、「人」が「人」であり、「地」が「地」であること、それ自身のことである。
荘子のとらえる「天」とは、「あるがまま」のことであり、分別(因果的思惟)を超えたところにあるということになる。
「天」の境地から物事を考えるということは、単に一切のことをそのまま肯定するということになる。
人間において「我」であることを我は尊重するが、「我」とはたまたまの現象でしかない。すべての「我」が我であるという意味において同一であるということが「天」であるということ。
個々の人々が「我」を主張するがゆえに「混沌」が起きるが、その混沌をそのまま自己の内面のこととして受け入れることが必要であるとする。
つまり、「天」とは超越した概念などではなく、そのもの自身の持つ「原理」であるということに思いをいたすように諭している。
ここで重要なことは、荘子は「神」を否定していることだけでなく、「理智」をも否定している。
この精神的基盤はカミュの不条理に通じる。カミュは「世間と自己との気晴らしのなかに埋没している人間が突如として不条理に目覚める時、一個の渾沌として世界を前にする」「幻想も希望も不意に失われると、人は自己が異邦人であることを悟る」
天地を揺るがす万籟の響きに我を忘れる子綦と、カミュが描く異邦人の中のムルソー(「異邦人」の主人公)には共通する苦しみと安らぎがある。