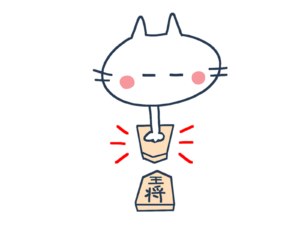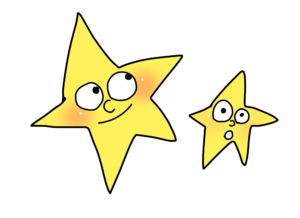「奉教人の死」と「二人の稚児」
芥川龍之介のバックボーンは、芳醇な言葉の才能と、そしてあふれんばかりの知識だなと、つくづく感じさせられます。「侏儒の言葉」などに端的に表れています。
「奉教人の死」とは、彼の「切支丹」物の一つになります。とくに有名なのが「煙草と悪魔」ではないでしょうか。「さまよえる猶太人」も、実に面白い視点だとつくづく感心してしまいます。
「奉教人の死」は「ろおれんぞ」と兄貴分の「しめおん」が、主たる役割を担っています。そこに傘張の娘が出てきて懐妊することから「ろおれんぞ」が疑われ破門され乞食に身をやつすけれど、実は傘張の娘の嘘であることが分かるのは「ろおれんぞ」が死に至る直前であるという話です。
非人に身をやつしても、身の潔白を訴えるわけでもなく、御主「ぜす・きりしと」の御加護を祈り続けていたが、長崎の町が大火にあった夜に傘張の娘が生んだ女児を助けるために自らの命を犠牲にするという話であるのだけれど、その語り口調が「安土桃山時代の京阪地方の話し言葉で描いた作品」だそうで、なんとも言えずに引き込まれてしまう作品です。
かたや、谷崎潤一郎の「二人の稚児」は、宗教とは言え、こちらは比叡山になります。千手丸と瑠璃光丸は、宗教的な戒律(主としては女人禁制のことや俗界の淫らさを忌避すること)に対する疑念を持ち、千手丸がこっそり下界を探索に出かけて、人さらいにさらわれ商家の下男として売られ、その家の婿養子になる。
しかし、千手丸は下界に住んでみると比叡山でいうような煉獄の地ではなく、むしろパラダイスであると瑠璃光丸に、下界に来るように誘う。
しかし、瑠璃光丸は、その誘いを拒絶して雪の降るさなかに比叡山の山奥に昇ると白い鳥が怪我をして苦しんでいる、その鳥を抱きしめながら話は終わるわけです。その最後は、あたかもルーベンスの絵を見ながら死にゆくネロとパトラッシュのような終末になっています。
根底に流れているテーマは、芥川にも谷崎にも共通しているように感じるのです。文学の力は、人の生き方への共感(あるいは、なぞれること)が得られることと思っています。