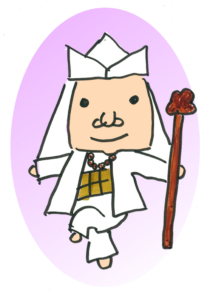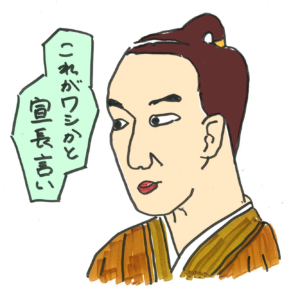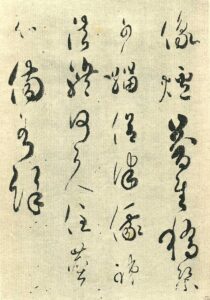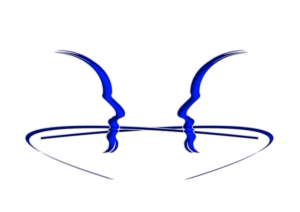七十路を「ななそじ」と読む
2023年7月8日
いままで「70代が見る景色」としていましたが、風情を重んじて「七十路」と改めました。 あっけなく 七十路となる 青畳 この俳句は「岡崎えい」による。「えい」は明治26年生まれ。雙葉女学校に通うも中退した模様。銀座2丁目で […]
「過去の歴史を見出した」過去の歴史
2024年11月19日
江戸時代を代表する国学者の一人である本居宣長(1730~1801年)は、日本社会が古代以来中国大陸からもたらされた文化や風習にまみれてしまったことを悲嘆します。 宣長は、仏教や儒学など、中国大陸からの影響を「漢意(からご […]
「奉教人の死」と「二人の稚児」
2023年6月5日
芥川龍之介のバックボーンは、芳醇な言葉の才能と、そしてあふれんばかりの知識だなと、つくづく感じさせられます。「侏儒の言葉」などに端的に表れています。 「奉教人の死」とは、彼の「切支丹」物の一つになります。とくに有名なのが […]
「看板」と勝手な記憶
2023年9月12日
2023年9月3日の夕焼け。浅草寺が真っ赤に燃えていました。 で、池波正太郎の「看板」を、おそらく20年ぶりくらいで再読しました。この「看板」は大好きで人にも勧めてきましたが、再度読んでみると、ずいぶん記憶と違っていたの […]
スタインベックを読んで
2025年1月20日
スタインベックはカリフォルニア州モントレー郡サリナスで1902年に生まれた。「赤い小馬」によると、ジョディは10歳となっている。ということは、時代は1912年。日本は明治45年であった。7月30日から大正元年になる。 ニ […]