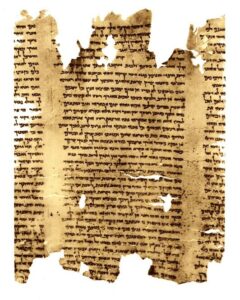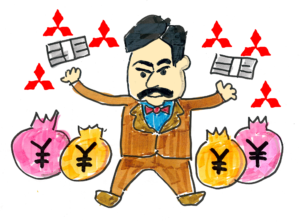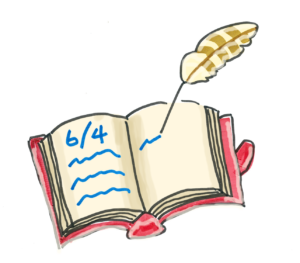2023年9月25日
1947年、死海の北西(ヨルダン川西岸地区)にあるクムラン洞窟などで発見された972の写本群の総称。 ヨルダン川西岸、死海に近いクムランという地域にある11の洞窟から、現時点で900巻前後の写本が見つかっており、断片の総 […]
2024年12月5日
石丸伸二が旅する「リハック旅」に東金が登場した。 ついでに「東金」を少し調べてみた。名前の由来は「鴇(とき)が根」に由来するといわれ、そこから「東金」になったらしいとのこと。 「東金城は往古上総介の属館なりしが後年千葉氏 […]
2023年11月17日
八幡市といえば、エジソンの電球のフィラメントに、当初、八幡の「八幡竹」が使われた。ついでの話として、八幡太郎義家は石清水八幡で元服したことから命名されている。 という八幡市で33歳の女性が市長になりました。自民・公明・立 […]
2023年12月5日
近代日本には三井、岩崎、住友などの財閥が存在したが、それを上回ったのが天皇財閥であった。天皇財閥とは日本銀行(過半数を超える大株主)、満鉄、横浜正金銀行、日本郵船などの国策会社を株式を通じて支配した。 天皇主権説は皇祖皇 […]
2024年6月4日
ワディ・エル・ジャラフという4000年以上前の古代遺跡がある。 2013年、歴史的発見がなされた。世界最古のパピルス文書「紅海文書」が30巻見つかった 何かとお騒がせなカイロ(大学)の近くだ。ワディ・エル・ジャラフはその […]
2024年1月15日
文京区小日向で3体の遺骨 260年の間、人口100万人の大都市だった江戸(東京)の地下にトンネルを掘れば墓地に当たることは少なくない。その結果、景気が良くなると人骨の収蔵が増えるという。 文京区小日向1丁目23番地:丸ノ […]
2025年2月4日
「コリーニ事件」はamazonのプライムで無料で見られるので、ずいぶん前に途中まで見ましたが中断していました。どのみち、新米弁護士が大活躍して黙秘を続ける被疑者の無実を勝ち取るぐらいのものだろうと思っていましたし、明らか […]
2023年8月13日
小野篁(たかむら)は実在した。生年は802年で、死没が852年。 六国史では、「日本後記」「続日本後記」「日本文徳天皇実録」に含まれる時代を生きた。「日本後記」は全40巻のうち10巻しか現存しておらず、「続日本後記」含め […]
2023年9月28日
藤原良相(813-867)は、冬嗣の五男。兄に良房がいる。官位は正二位の右大臣。西三条大臣と号した。834年、仁明天皇(808-850)に召し出されて仕えた。 承和の変において皇太子・恒貞親王の座所を包囲している。恒貞皇 […]
2023年11月21日
向日市一帯では、古瓦がたくさん出ることは古くから知られていた。形の好い古瓦は愛蔵家がコレクションにしていた。 研究者によると、大極殿・朝堂院付近に難波宮瓦が多く出、その周辺に平城宮瓦が多く出ているようです。長岡宮で焼いた […]