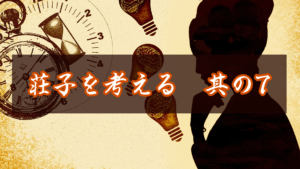大鏡:其15《帝紀-後一条天皇》
この天皇は今上天皇(つまり世継と繁樹は後一条天皇の御代に出会ったということ)。生母は藤原彰子で、藤原道長の長女。皇太后宮。 4歳で立太子。9歳で即位。29歳で崩御。 後見役は祖父でもある入道道長。叔父は関白左大臣頼通と内 […]
大鏡:其13《帝紀-一条天皇》
円融天皇の第1皇子。生母は藤原詮子(藤原兼家の次女)。5歳で東宮に立ち、7歳で即位した。治世は25年。詮子は17歳で円融天皇に入内し、19歳で一条天皇を生んだ。藤原詮子は、道隆、道兼、道長の母・時姫と同母の兄妹であった。
大鏡:其12《帝紀-花山天皇》
第65代 花山天皇(968-1008) 冷泉院の第1皇子(生母は、藤原懐子・藤原伊尹(これただ)の長女)。2歳で立太子し17歳で即位した。治世は2年の19歳で出家した。その後、法皇として22年在世した。 藤原道兼が花山天 […]
大鏡:其07《帝紀-醍醐天皇》
第60代 醍醐天皇(885-930) 宇多天皇の第1皇子といい生母は藤原胤子(いんし)。胤子は藤原高藤の息女。9歳で皇太子に立った。11歳で元服し13歳で天皇に即位した。夜の御殿から冠を被って自ら践祚の宣言をしたとのこと […]
大鏡:其02《帝紀-文徳天皇》
第55代 文徳天皇(827-857) 文徳天皇は仁明天皇の第一皇子である。母は藤原順子で、藤原冬嗣の息女であった。 842年(承和9年)に元服し、同じ年に皇太子になる。このとき16歳。 文徳天皇は更衣の后・静子所生の第一 […]
「枕草子」が描いた世界《其の06》
宮に初めて参りたるころ、ものの恥づかしきことの数知らず、涙も落ちぬべければ、夜々参りて、三尺の御几帳の後ろに候ふに、絵など取り出て見せさせ給ふを、手にてもえさし出づまじう、わりなし。 177段 清少納言が藤原定子の女房と […]
荘子を考える:斉物論《其の11》
物無非彼:物は彼れに非らざるは無く 物無非是:物は是れに非ざるはなし 自彼則不見:彼よりすれば則ち見えざるも 自知則知之:自から知れば則ち之を知る 物は「あれ」でないものはなく、同時に「これ」でないものもない。 人間は自 […]
「枕草子」が描いた世界《其の10》
207段は「笛は横笛、いみじうをかし」で始まる。 遠くから聞こえて、だんだん近づいてくるのもいいし「近かりつるが、遥かになりて、いとほのかに聞ゆるも、いとをかし」とし、懐に携えていつでも吹けるようにしているようなしゃれた […]
荘子を考える:斉物論《其の07》
大知閑閑:大知は閑閑(かんかん)たり 小知閒閒:小知は間間(かんかん)たり 大言炎炎:大言は炎炎(たんたん)(淡淡)たり 小言詹詹:小言は 詹詹(せんせん)たり 「大知」のあるものは、ゆったりとして落ち着いているが、「小 […]