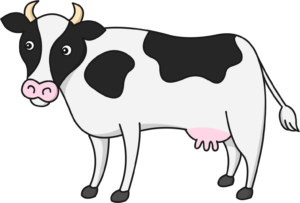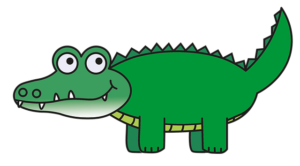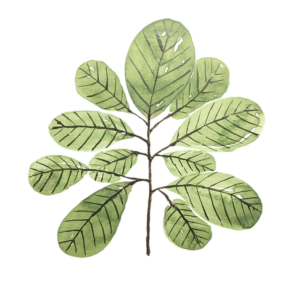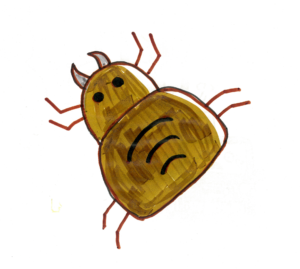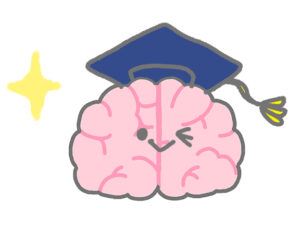牛乳を飲むということ
動物が母乳を飲むのは、子供の時だけに限られている。人間も母乳を飲む時期は限られている。にもかかわらず、大人になっても牛乳を飲み続けている。 トルコで見つかった8500年前の陶器から乳脂肪の痕跡が使っている。 同じ場所から […]
近親交配を回避する仕組み
近親交配を回避する受粉の新たな仕組みを解明したという2010年の記事があった。奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科細胞間情報学の研究で、ナス科植物のペチュニアが、動物の免疫系によく似た多種類のタンパク質を動員 […]
光合成による水の分解
光合成がどのような仕組みで行われているのかについては、まだ正確にはわかっていない。光合成は太陽光を利用して二酸化炭素と水を糖に変え、廃棄物として酸素を放出する。 光合成のおかげで地球は酸素の供給を得られている。酸素は水を […]
Y染色体がいずれ消滅?
性染色体というのがあって、X-Xの組み合わせだと「女」になり、X-Yの組み合わせだと「男」になる。これは、動物だけではなく植物にも共通している。 このY染色体が劣化減少していると、かねてから言われている。 哺乳類のY染色 […]
犬が友になり世界へ広まる
イヌは同じような環境で育てられたオオカミに比べて社交的である。社交的なイヌでは、GTF2IとGTF2IRD1という2つの遺伝子に変異があることが明らかになった。 ヒトでは、これらの遺伝子の変異は、妖精のような独特な顔つき […]
ネアンデルタール人の新事実が解明進行中
多くの「ヒト属」の種はアフリカで誕生し、まずヨーロッパや中東へ、そしてさらに遠方へ移り住んだ。ネアンデルタール人が移動したのは20万年前。現生人類は6万年ほど前に移動した。ネアンデルタール人と現生人類は2万年ほど共存して […]
知能指数の高い子は成長して成功するのか
IQの高い子どもは大人になるとその多くが普通の人生を送っていることが分かってきている。スタンフォード大学のターマン博士(1877-1956)は、IQ135以上の天才児1528名を60年にわたって調査した結果、ほとんどは実 […]