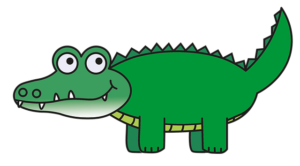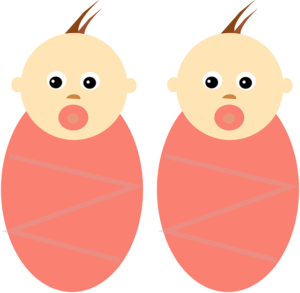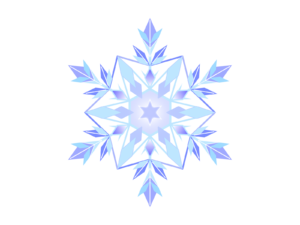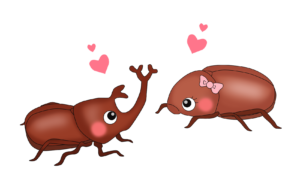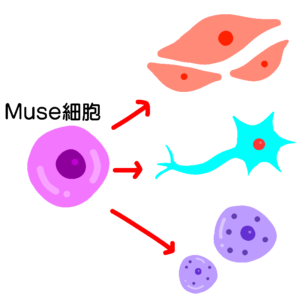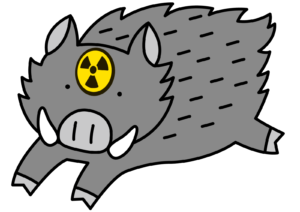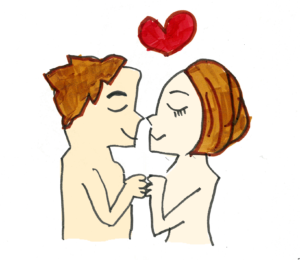ゴールトンと双子と遺伝子
2023年8月25日
フランシス・ゴールトンといえば、人間の才能が遺伝によって受け継がれると主張した人物で、はじめて「優生学(Eugenics)」という今日、きわめて評判の悪い言葉を使い、広めたことでも知られている フランシス・ゴールトンは、 […]
カブトムシのツノのゲノム解析
2023年7月17日
MITテクノロジーレビューの2023年7月13日の記事にカブトムシの角に関する記事がありました。 基礎生物学研究所、金沢大学、モンタナ大学などのチームはカブトムシのゲノムとミトコンドリアを解読してツノ形成の遺伝的メカニズ […]
イノシシだけが放射性物質に汚染されている
2023年9月13日
イノシシの放射線レベルは時間の経過とともに減少していくはずなのに、イノシシはその地域の他の動物と違って放射性物質で汚染され続けているという。 科学者は、その原因として「トリュフ」だと考えていた。セシウム137の半減期は3 […]
チンパンジーが長文をタイプする確率
2024年11月12日
チンパンジーが「Bananas」という簡単な単語を偶然に書き上げるには、1頭のチンパンジーが、その生涯にタイピングをし続けて打てる確率は5%だそうだ。 「I think, therefore I am.」となると地球上の […]
性決定の不思議な世界
2024年4月23日
ヒトの性のデフォルトは「女性」だそうだ。それをY染色体のSRYという遺伝子が妨害することで「男性」にしている。つまり、ヒトは全て女性になりたがっているということ。 Y染色体は、今に至る間に突然変異などで淘汰され、染色体自 […]
生物が大型化した理由
2024年6月19日
なぜエディアカラ紀に生物の身体が複雑化・大型化したのか、その理由はよく分かっていない。 ちなみに、エディアカラ紀とは、新原生代クライオジェニアンの終わりから古生代カンブリア紀の始まりまでの約6億2000万年前〜約5億42 […]