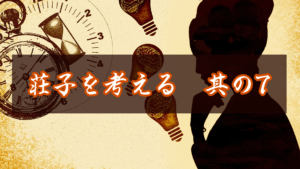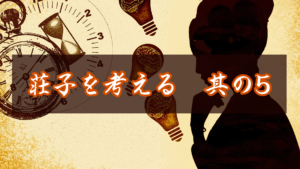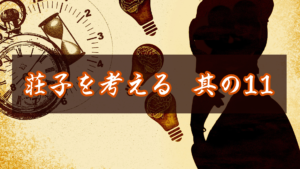「枕草子」が描いた世界《其の14》
上の御前の、柱によりかからせ給ひて、すこし眠らせ給ふを、「かれ見奉らせ給へ。今は明けぬるに、かう大殿籠るべきかは。」と申させ給へば、「げに。」など宮の御前にも笑ひ聞こえさせ給ふも知らせ給はぬほどに、長女が童の、鶏を捕らへ […]
「枕草子」が描いた世界《其の02》
春は、あけぼの夏は、夜秋は、夕暮れ冬は、つとめて(早朝) 「春はあけぼの、やうやう白くなりゆく山際すこしあかりて、紫だちたる雲の細くたなびきたる」とパステルで描いた絵のような色使い。 道元が鎌倉時代に「春は花 夏ほととぎ […]
「枕草子」が描いた世界《其の08》
「清少納言集」というのがあって、自らが書いたものではなく鎌倉中期に成立したとされているようです。和歌が31首あるものと42首あるものがあって、いずれも宮内庁が所有している。 和歌も清少納言が詠んだかは不明で、確かに、いく […]
荘子を考える:斉物論《其の07》
大知閑閑:大知は閑閑(かんかん)たり 小知閒閒:小知は間間(かんかん)たり 大言炎炎:大言は炎炎(たんたん)(淡淡)たり 小言詹詹:小言は 詹詹(せんせん)たり 「大知」のあるものは、ゆったりとして落ち着いているが、「小 […]
大鏡:其05《帝紀-光孝天皇》
第58代 光孝天皇(830-887) 第58代天皇。第54代の仁明天皇の第3皇子で、第55代文徳天皇の弟になる。生母は藤原総継の息女の藤原沢子。その後、清和、陽成と文徳天皇の皇統が続くが53歳にして一品に昇進し、55歳で […]
荘子を考える:逍遥遊《其の05》
吾有大樹:吾に大樹あり 人謂之樗:人これを樗(ちょ)と謂う。 其大本擁腫而不中繩墨:其の大本は擁腫(ようしょう)して縄墨(じゅうぼく)に中(あ)たらず 其小枝卷曲而不中規矩:その小枝は巻曲(けんきょく)て規矩(きく)に中 […]
「枕草子」が描いた世界《其の17》
紫式部は、清少納言の「枕草子」を熟読していた節が、散見される。 屋の上は、ただおしなべて白きに、あやしきしづの屋も雪にみな面隠しして、有明の月のくまなきに、いみじうをかし。 白銀などを葺きたるやうなるに、水晶の滝などいは […]
「枕草子」が描いた世界《其の07》
16か17歳の藤原定子は、清少納言を女房にしたのには、明確な理由があったはずである。 清少納言の父親である清原元輔も歌人であったし、祖父の清原春光に関しては詳細が不明となっているが、曽祖父の清原深養父は、勅撰歌人であり勅 […]
大鏡:其04《帝紀-陽成天皇》
第57代 陽成天皇(868-949) 清和天皇の第1皇子。母は藤原高子。2歳で東宮に立ち9歳で即位した。治世は8年で退位してから二条院にいた。退位後65年の81歳で崩御した。法事の願文に「釈迦如来の一年の兄(このかみ)」 […]
荘子を考える:斉物論《其の10》
故有儒墨之是非:故に儒墨の是非有り 以是其所非 而非其所是:以て其の非とする所を是として其の是とする所を非とす 欲是其所非而非其所是:其の非とする所を是として其の是とする所を非とせんと欲する 則莫若以明:則ち明を以てする […]